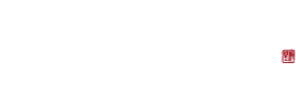墓じまい後に永代供養を行う手順|それぞれの違い・メリットも

この記事を書いた人
近年、家族の在り方や生活環境の変化により、先祖代々から受け継いできたお墓の管理が難しくなるケースが増えてきました。そのため、遺族や子孫の負担を軽減しつつ、先祖供養を続けられる、「墓じまい」と「永代供養」を組み合わせた供養方法が注目されています。
当記事では、墓じまいと永代供養の違いや永代供養にするメリット、手続きを円滑に進める手順を分かりやすく紹介します。
目次
1. 墓じまいと永代供養の違い

近年、生活スタイルや家族構成の多様化により、お墓を十分管理し切れない家庭が増えてきました。そのため、お墓を整理する「墓じまい」を行い、その後「永代供養」を選ぶケースが注目されています。2つは混同されることが多いものの、目的が異なります。
墓じまいとは、既存のお墓を撤去し、更地に戻す手続きです。お墓に納められている遺骨を取り出し、墓石を解体して使用権を管理者に返還します。ただし、墓じまい後は遺骨を新たな供養方法で安置しなければなりません。
一方、永代供養とは、お寺や霊園が遺骨の管理や供養を行う方法を指します。一定期間は契約した納骨スペースに遺骨が安置され、その後、他者と合祀される形式が一般的です。お墓を持たなくても故人を供養しつつ、家族や親族がお参りを続けられる方法として人気があります。
このように、墓じまいは「お墓を片づける手続き」、永代供養は「遺骨を管理・供養する方法 」という違いがあります。それぞれの役割を理解し、自分や家族の事情に合った方法を選ぶことが大切です。
2. 墓じまい後に永代供養を行うメリット3選

墓じまい後に永代供養を行うことには、多くの利点があります。特にお墓の管理負担や経済的な問題を解消し、将来の不安を軽減できる点が代表的です。以下では、永代供養を選ぶメリットを3つ解説します。
2-1. お墓の管理にかかる手間がなくなる
永代供養では、お墓の管理をすべてお寺や霊園に任せられるため、遺族が直接管理作業を行う必要がありません。通常のお墓では、定期的な清掃や補修が必要となりますが、永代供養の場合はこれらを施設側が代行します。
特に、お墓が遠方にある場合や高齢のため清掃や移動が難しい場合、管理を任せることによって肉体的・精神的な負担を軽減できるでしょう。なお、個別のお墓がないタイプでも、お墓参り自体は可能です。居住地の近くを選べば、故人を偲ぶ時間を確保しやすい点もメリットと言えます。
2-2. お墓の費用負担が軽減される
合祀を前提とした永代供養では、最初の契約時に一括で費用を支払うことで、その後の管理費は発生しないのが一般的です。通常のお墓では、年間の管理費や運営費に加え修繕費が必要となりますが、永代供養ではこれらの費用がすべて初期費用に含まれます。
さらに、永代供養では宗派を不問とするところが多く、檀家制度から離れることも可能です。檀家を抜ければ、寄付や法要の際のお布施といった追加負担が減り、経済的な負担を大幅に軽減できるでしょう。現在のお墓の維持が難しい方や、負担を減らしたいと考えている方は、検討の余地があります。
なお、寺院や霊園にある墓地の土地を永代にわたって使用する「永代使用」では、永代供養が付帯するものの、墓地の維持管理を目的とした「護持会費」が必要です。このように、永代供養だからといって必ずしも管理費が発生しないわけではないことも覚えておきましょう。
2-3. お墓の継承者の心配がなくなる
核家族化や少子化の影響で、お墓を引き継ぐ継承者がいないケースが増えています。永代供養を選べば、供養や管理をお寺や霊園が代行するため、継承者がいなくても安心です。
また、無縁墓になる心配がない点も永代供養の大きなメリットです。お寺や霊園が責任を持って供養を続けるため、先祖代々のお墓が野ざらしで放置される恐れがありません。これにより、故人や先祖への供養に関する精神的な不安が解消されます。
3. 【8STEP】墓じまいをして永代供養を行う手順・流れ

墓じまいをして永代供養に移行する際には、必要な手続きの順番通りに進めるとスムーズです。以下では、必要な準備や注意点を含めた具体的な流れを、8つのステップに分けて解説します。
3-1. 家族・親族に墓じまいの相談をする
墓じまいは家族や親族全体に関わる問題です。お墓の承継者であっても、独断で進めるとトラブルになりかねないため、まずは親族と十分に話し合いを行いましょう。
親族の考え方によっては、「ご先祖様に失礼」「供養の形式を変えるのは抵抗がある」といった意見が出ることもあります。そのため、費用や手続きに関する情報を共有し、理解を得ることが大切です。墓じまいにかかる費用分担や今後の供養の方法についても具体的に話し合うと、親族間の合意を得やすくなります。
3-2. 寺院・霊園に墓じまいの相談をする
親族の同意を得られたら、お墓を管理している寺院や霊園に相談しましょう。菩提寺にあるお墓の場合は、離檀料が必要となることがあります。離檀は寺院側にとってあまり歓迎できる事態ではないため、円満に進めるには理由を丁寧に説明し、同意を得ることが重要です。
離檀料の相場や支払い方法についても事前に確認し、寺院や霊園との関係を良好に保つよう努めましょう。必要書類や手続きの詳細も忘れず確認してください。
3-3. 新たな永代供養先を決める
永代供養先を選ぶ際は、施設の信頼性や供養方法、費用、アクセスの利便性などを考慮するとよいでしょう。インターネットでの検索やパンフレットの取り寄せだけでなく、実際に現地を訪れて雰囲気を確かめることが大切です。
施設ごとの供養期間や管理体制、宗派の違いが利用に影響する場合もあるため、十分に調査する必要があります。また、管理費や追加料金が発生する条件についても、事前に確認しておくと安心です。
3-4. お墓の撤去業者を決める
お墓の撤去は専門の石材店に依頼するのが一般的です。お寺によっては利用できる石材店が指定されています。自分で探す場合は、業者の口コミや評判を調べて信頼できる業者を選ぶと、トラブルを未然に防げます。
費用は墓石の大きさや外柵の有無によって異なるため、複数の業者から見積もりを取り、比較検討すると安心です。契約後の追加費用を防ぐためにも、作業内容や料金を事前に詳細に確認しておきまましょう。
3-5. 墓じまいに必要な行政手続きを進める
墓じまいには「改葬許可証」の取得が必要です。まず、現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を取得し、次に新しい供養先から「受入証明書」をもらいます。この2つを添えて「改葬許可申請書」を市町村役場に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
自治体によっては手続きの方法が異なる場合があるため、事前に役所へ問い合わせるとスムーズです。書類に不備があると手続きが遅れます。早めに必要な項目を確認しておくとよいでしょう。
3-6. 閉眼供養を執り行う
墓じまいを行う前に、「閉眼供養」と呼ばれる儀式を行います。閉眼供養は墓石に宿った魂を抜き取るための法要で、お墓に花や線香を供え、僧侶に読経してもらうのが一般的です。
閉眼供養は、仏教の教えに基づく重要な儀式であり、これを行うことでお墓に宿った故人の魂を新たな供養先へ移す準備が整います。閉眼供養が済んでいないと、墓石の撤去作業をしてくれない業者も少なくありません。
3-7. お墓の撤去・解体を行う
閉眼供養後、石材店に墓石の解体と撤去作業を依頼します。撤去した区画は更地に戻し、最終的に墓地管理者に返還します。お墓の状態によっては、作業が長引いたり追加料金が発生したりするため、事前に見積もり内容を精査しておきましょう。
墓石の運搬や処分についても、業者に確認しておくと安心です。また、撤去後に発生した廃材やゴミについても、どのように処理するかを把握しておかなければなりません。
3-8. 新たな永代供養先に遺骨を納める
最後に、永代供養先に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。新しいお墓に「開眼供養」を行うのもこのタイミングです。
なお、遺骨の保存状態が悪かったり土と混ざっていたりすると、納骨前に洗浄が必要になる場合があります。施設側と納骨のスケジュールや手続きについて十分に確認し、滞りなく埋葬を終えられるようにしましょう。
まとめ
墓じまいから永代供養への流れをスムーズに進めるためには、適切な準備と手続きが欠かせません。まずは家族や親族との相談から始め、寺院や霊園との話し合いや永代供養先の選定を丁寧に行いましょう。
墓じまいには行政手続きや閉眼供養、墓石撤去など多岐にわたる作業が含まれますが、これらを1つずつ確実に進めていけば、安心して供養を継続する環境を整えられます。ぜひ当記事を参考にして、故人や先祖を大切にする新たな供養の形を検討してみてください。
了聞では、全国各地の墓じまいをフルサポートいたします。墓じまいを検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。