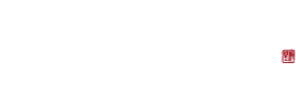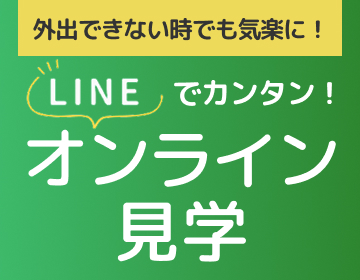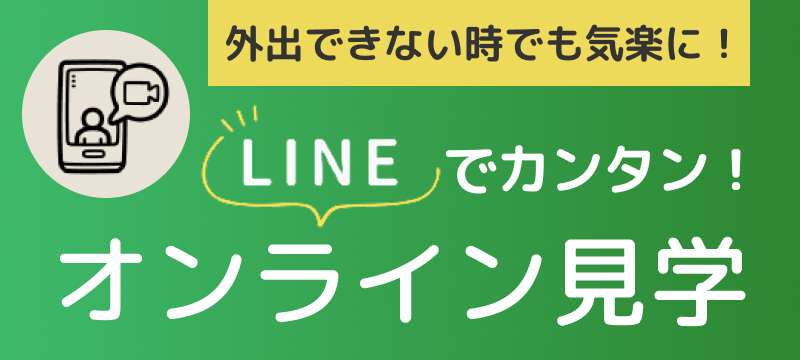増上寺の歴史・由来を年表付きで分かりやすく紹介!

この記事を書いた人
東京・芝公園にある増上寺は、600年以上の歴史を持つ浄土宗の大本山です。徳川家の菩提寺として発展し、江戸時代には日本有数の大寺院となりました。現在も東京タワーを背景にした美しい風景とともに、多くの参拝者を迎えている人気の寺院の1つです。
当記事では、増上寺の歴史や見どころなどを紹介します。室町時代の創建から戦国・江戸・明治・現代に至るまでの歩みをたどり、歴史と文化が息づく名刹を紐解いていきましょう。知識を得てから訪れれば、増上寺の魅力をより深く堪能できます。
目次
1. そもそも「増上寺(ぞうじょうじ)」とは?

増上寺とは、東京都港区芝公園にある浄土宗の寺院で、大本山に位置付けられている格式の高い寺院です。正式名称は「三縁山広度院増上寺」です。1393年(明徳4年)、室町時代に酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人が開山しました。もともとは現在の千代田区平河町付近にありましたが、徳川家康の江戸入府を機に現在の場所へ移転しました。
江戸時代には徳川将軍家の菩提寺として発展し、巨大な寺院となりました。現在も本堂をはじめ、重要文化財の門や徳川家の霊廟などがあり、多くの参拝者が訪れています。特に東京タワーを背景にした風景は観光スポットとしても人気です。
1-1. 増上寺の宗旨
宗旨とは、宗教の基本的な教えや信仰の内容を指します。仏教にはさまざまな宗派があり、それぞれが異なる教義を持っています。増上寺の宗旨は「浄土宗」で、これは法然(ほうねん)上人によって1175年(承安5年)に開かれた宗派です。
浄土宗の教えの中心は、「阿弥陀仏の浄土へ往生するために、ほかの行をまじえずただひたすらに称名念仏を修する」という 「専修念仏」です。人格を高めて社会のために尽くし、明るく安らかな毎日を送りながら浄土に生まれることを願うこの信仰は多くの人々に受け入れられ、日本全国に広がっていきました。
増上寺のご本尊は「無量の光と慈悲を持つ仏」とされる阿弥陀如来です。徳川家康が戦の際に持ち歩いた「黒本尊」と呼ばれる阿弥陀如来像も安国殿に安置されており、勝運のご利益があるとされています。
1-2. 増上寺の寺格
寺格とは、寺院の格式や宗派内での位置付けを示すものです。仏教の寺院には「本山」「別格本山」「大本山」「総本山」などの階級があり、宗派ごとにその役割が異なります。浄土宗では、宗派の中心となるのが「総本山」、次に位の高い寺院が「大本山」です。
浄土宗の総本山は京都の知恩院ですが、増上寺はそれに次ぐ七大本山の1つとして、日本全国の浄土宗寺院を支えています。大本山の中でも、知恩院と並び僧侶の育成機関としても機能している点で、別格とされているお寺です。
現在も増上寺では、浄土宗の僧侶を目指す人が必ず受ける修行が行われ、夏と冬には全国から多くの修行者が集まります。また、増上寺は格式の高さだけでなく、広大な境内や諸堂宇の整備を進めるなど、現代においても宗派の中心寺院としての役割を果たす存在です。
2. 増上寺の歴史|室町時代から平成時代までの歩み

増上寺は、室町時代に創建されてから600年以上の歴史を持ちます。安土桃山時代には徳川家との縁が生まれ、江戸時代には将軍家の菩提寺として繁栄しました。明治時代以降は戦火や政策の影響で苦難を経験しながらも、復興を遂げてきた寺院です。その歩みを時代ごとに紹介します。
2-1. 【室町時代/1393年】増上寺の開創
増上寺は、1393年(明徳4年)に酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人によって創建されたお寺です。当初は武蔵国豊島郷貝塚(現在の千代田区平河町付近)に建立され、浄土宗の正統な念仏道場として位置付けられました。
この時代、関東では浄土宗が広まりつつありましたが、正式な学問・修行の場は少なかったため、増上寺は関東における浄土宗の教学の拠点として発展します。やがて、多くの僧侶が修行する寺院となり、地域の信仰の中心となっていきます。
2-2. 【安土桃山時代/1590年~1598年】徳川家との結縁
1590年(天正18年)、徳川家康が関東に移封された際、増上寺の住職であった源誉存応(げんよぞんのう)上人と深く親交を結びました。これにより、増上寺は徳川家の菩提寺として定められます。
1598年(慶長3年)には、家康の命により、寺は現在の芝公園に移転しました。この移転は、江戸の発展計画の一環でもあり、増上寺が徳川家にとって重要な寺院となった証でもあります。以降、幕府からの手厚い庇護を受け、増上寺の規模はさらに拡大していきました。
2-3. 【江戸時代/1603年~】増上寺の隆盛
1603年(慶長8年)に徳川家康が江戸幕府を開くと、増上寺は幕府の庇護を受けて急速に発展します。朝廷から勅願所として認められたほか、1610年(慶長15年)には存応上人には「普光観智国師」の称号が授けられました。
浄土宗の総務を統括する総録所の設置に加え、幕府からは多くの寺領が寄進され、学寮や僧侶の修行施設も整備されました。最盛期には120以上の堂宇や100軒以上の学寮が立ち並び、3,000人以上の僧侶が修行に励んでいたと言われています。
2-4. 【明治時代~大正時代】増上寺の試練と復興
明治時代に入ると、増上寺も廃仏毀釈の影響を受け、厳しい状況に直面しました。境内の広大な土地の多くが没収され、一部は政府の施設として転用されたためです。さらに、1873年(明治6年)と1909年(明治42年)には大火に見舞われ、大殿を含む多くの建物が焼失しました。
しかし、1875年(明治8年)には大本山に列せられ、伊藤博文ら新たな檀家を迎えたことにより復興が進みます。大正時代には焼失した堂宇の再建が進み、1921年(大正10年)には新たな大殿が完成しました。
2-5. 【昭和時代~平成時代】増上寺の再興と新時代の幕開け
昭和時代、さらなる発展に向けて尽力していた増上寺は、第二次世界大戦の戦火により大きな被害を受けることになります。特に1945年(昭和20年)の東京大空襲では、ほとんどの伽藍が焼失し、江戸時代から続く堂宇の多くが失われました。
しかし、終戦後の1952年(昭和27年)には仮本堂を設置し、復興への第一歩を踏み出します。1974年(昭和49年)には悲願の新大殿が完成し、平成に入るとさらなる整備が進められました。1989年(平成元年)には開山堂(慈雲閣)が再建され、2009年(平成21年)には圓光大師堂と学寮が完成、2010年(平成22年)には安国殿の再建が叶いました。
こうして、増上寺は歴史を重ねながらも、新たな時代へと歩みを進めています。
3. 増上寺の見どころ

増上寺には、歴史的価値の高い建築や仏像が多く残されています。境内を歩きながら、徳川家とのゆかりや仏教の教えを感じられるスポットを巡ってみましょう。
●三解脱門
1622年(元和8年)に建立された増上寺の表門で、東日本最大級の木造門です。東京大空襲でも焼失を免れた貴重な建築で、2022年(令和4年)に創建から400年を迎えました。門をくぐると「むさぼり・いかり・おろかさ」の3つの煩悩を解脱できるとされるのが、この名の由来です。
●大殿
増上寺の本堂で、ご本尊の阿弥陀如来が安置されています。1974年(昭和49年)に再建された鉄筋コンクリート造りの堂内は広々としており、読経の響きがよく伝わります。境内からは東京タワーが背景に見え、歴史と現代の対比を楽しめるスポットとしても人気です。
●安国殿
戦後に仮本堂として使用していた建物を移築したもので、現在は徳川家康ゆかりの「黒本尊」を安置しています。黒本尊は家康が戦に携帯して勝運を祈願したとされる秘仏で、長年の線香の煙によって黒ずんだことからこの名で呼ばれています。黒本尊は、お正月・5月・9月の15日にのみ開帳されます。
このほかにも、増上寺には重要文化財の「経蔵」や「鐘楼堂」、歴代将軍が眠る徳川家霊廟など、見どころが豊富です。境内をゆっくり散策しながら、歴史の深さを感じてみてはいかがでしょうか。
まとめ
増上寺は、室町時代に創建され、徳川家の菩提寺として発展した浄土宗の大本山です。江戸時代には日本有数の大寺院となり、多くの僧侶が修行を行いました。明治時代には廃仏毀釈の影響を受け、昭和の戦災で伽藍を焼失しましたが、その後復興し現在も多くの参拝者が訪れています。
境内には、東日本最大級の木造門「三解脱門」や、阿弥陀如来を祀る「大殿」、勝運の仏として信仰される「黒本尊」を安置する「安国殿」など、見どころが満載です。ぜひ一度足を運び、歴史と文化を感じてみてください。