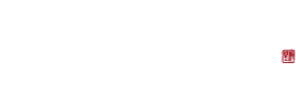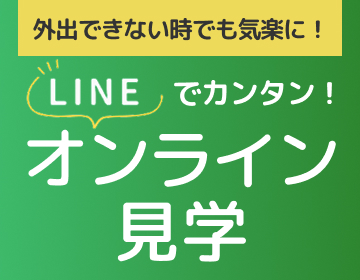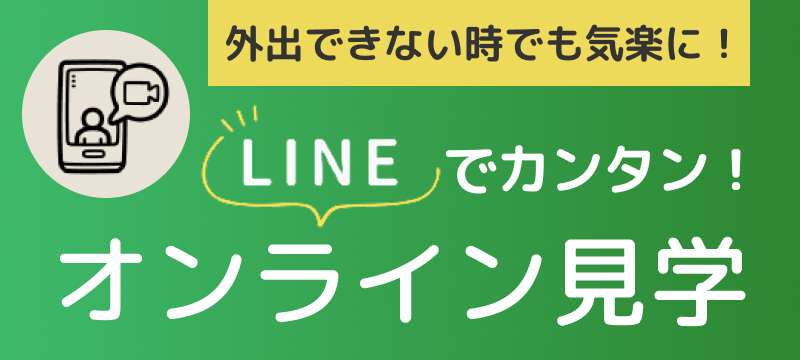年忌法要はいつまで行う?一般的な弔い上げ・省略のタイミング

この記事を書いた人
日本では、節目の年に故人の年忌法要を行う慣習があります。家族や親族が亡くなってからそろそろ一周忌が近づいてきて、「年忌法要はいつまで行えばよいのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、そもそも年忌法要とは何かを説明した上で、弔い上げや年忌法要を省略するタイミングを紹介します。年忌法要を行う年数の数え方をよく知らない方や、いつまで年忌法要を行えばいいかで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
目次
1. そもそも「年忌法要」とは?

年忌法要とは、節目となる年において、故人の祥月命日に行う追善供養のことです。故人が亡くなった翌年の一周忌をはじめとして、2年目の三回忌、6年目の七回忌といったように特定の年数ごとに行います。
年忌法要の数え方は、故人が亡くなった日を1回目の命日とする点に注意してください。2年目の三回忌のように、「○回忌」という表記では経過した年数に1を加えて数えます。
そもそも年忌法要を行う理由は、仏教に「十三仏信仰」という考え方があるためです。
十三仏信仰では死者は百箇日法要の後、一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・三十三回忌のときに仏や菩薩の裁きを受けるとされています。故人が死後の世界を無事に過ごせるよう、年忌法要を執り行って冥福を祈ることが、年忌法要を行う主な意味です。
回忌とは?年忌法要の数え方・弔い上げのタイミング・よくある質問も
1-1. 年忌法要と忌日法要の違い
法要には年忌法要のほかに、忌日法要があります。
忌日法要とは、故人の命日(忌日)を1日目として、特定の日数ごとに行う法要のことです。
忌日法要では、忌日から7日目の「初七日法要」をはじめとして、14日目の「二七日」から49日目の「七七日」まで7日ごとに法要を行います。七七日の後は、忌日から100日目に「百箇日法要」を行います。
忌日法要は百箇日法要で終わり、故人の忌日から1年後には一周忌を行うという流れです。
忌日法要は初七日法要から百箇日法要までの「忌日から1年以内に行う法要」、年忌法要は一周忌以降の「忌日から1年後以降に行う法要」と覚えておくとよいでしょう。
2. 年忌法要は「三十三回忌」まで行われるのが一般的!

年忌法要の中でも、最後の年忌法要は「弔い上げ」と言います。弔い上げをすると、故人はご先祖様の列に加わると考えられており、以降は年忌法要を行わなくなります。
弔い上げとする年忌法要は、三十三回忌にするケースが多い傾向です。しかし、三十三回忌を弔い上げとするのはあくまでも一般的な目安であり、宗派や地域によって弔い上げのタイミングはさまざまとなっています。
また、法要というと「家族だけでなく親族も集まって行うもの」というイメージが強いものの、必ずしも親族が集まって行わなければならないという決まりはありません。
ここからは、年忌法要をいつまで行うとよいかを分かりやすく解説します。
2-1. 年忌法要をいつまで行うかは宗派・地域によっても異なる
年忌法要をいつごろ弔い上げとするかは、信仰する宗派や地域によって異なります。
主な宗派における一般的な弔い上げのタイミングは、下記の通りです。
●真言宗
真言宗は十七回忌の後は二十三回忌を行わずに二十五回忌を行い、さらに二十七回忌を飛ばして、三十三回忌で弔い上げとします。弔い上げをせず、五十回忌や百回忌を行うこともあります。
●曹洞宗
曹洞宗は十七回忌の後に二十三回忌と二十七回忌を行うか、二十五回忌で1回にまとめて行います。その後、三十三回忌で弔い上げとすることが一般的です。五十回忌や百回忌を行う場合もあります。
●臨済宗
臨済宗は十七回忌の後に、二十三回忌と二十五回忌を行う地域と、二十七回忌のみを行う地域があります。どちらの場合も弔い上げは三十三回忌です。五十回忌や百回忌は行いません。
●日蓮宗
日蓮宗では十七回忌の後に、二十三回忌と二十七回忌を行う地域と、二十五回忌のみを行う地域があります。
日蓮宗では「故人の魂は常寂光土に行く」と考えられています。弔い上げという考え方がなく、執り行う人が亡くなるまで年忌法要を続けることが基本です。しかし、実際には三十三回忌で弔い上げとするケースが多いとされています。
●浄土真宗
浄土真宗の場合は、十七回忌の後に二十三回忌と二十七回忌を行うか、二十五回忌で1回にまとめて行います。その後、三十三回忌または五十回忌で弔い上げとすることが一般的です。
浄土真宗では、人は亡くなった後にすぐ極楽浄土に行くと考えられています。年忌法要は故人の供養ではなく、遺族が故人を偲ぶ場として執り行うことから、弔い上げ後も継続して回忌法要を行うこともあります。
2-2. 近年では七回忌以降の法要を省略する家庭も多い
近年は核家族化や親族間の距離の問題など、年忌法要を執り行うのが難しくなる事情があります。そのため、七回忌以降の法要を省略する家庭は増えている傾向です。
ただし、七回忌以降の省略と一口に言っても、下記のようにさまざまなケースがあります。
●三回忌で弔い上げとするケース
親族が揃って年忌法要を行うのは三回忌までとして、以降の法要は個人での供養に切り替えるやり方です。
●七回忌以降は規模を縮小するケース
七回忌以降は供養の規模を縮小し、一親等や二親等といった近しい間柄の親族間でのみ供養を行います。
●七回忌以降は節目となる年忌にのみ法要を行うケース
「十三回忌は省略して、十七回忌は親族揃って行う」といったように、節目となる年忌を選んで法要を行います。
七回忌以降の法要を省略するときは、自分たちにとってどのケースが適しているかを考えるとよいでしょう。
3. 年忌法要の主な種類

年忌法要をいつまで行うか考えるときは、年忌法要の種類を知っておくことが大切です。
年忌法要の主な種類として、一周忌から五十回忌までの法要を解説します。
●一周忌
一周忌は、故人が亡くなった翌年の祥月命日に行う最初の年忌法要です。「周忌」という数え方をするのは一周忌のみで、以降は「○回忌」と数えます。
一周忌でやることは親族や故人の友人を招き、お坊さんに読経してもらうことです。会食も行って、故人を偲びます。
●三回忌
三回忌は、故人が亡くなってから2年後の祥月命日、つまり一周忌の翌年に行う年忌法要です。
三回忌を行う時期は故人が亡くなった年と近いため、故人を偲びたいという方も多いでしょう。そのため、三回忌の法要は一周忌と同程度の規模で行うことが一般的です。
●七回忌
七回忌は、故人が亡くなってから6年後の祥月命日に行う年忌法要です。
七回忌になると故人が亡くなった年が遠くなり、招く親族の人数や法要の規模を縮小しても不自然ではなくなります。
また、七回忌以降は法要の併修を行えることもあります。
併修とは、「叔母の七回忌と、祖父の十三回忌を同じ日に行う」といったように、2件以上の法要をまとめて1日で行うことです。それぞれの法要の祥月命日が違っていても、どちらかの命日に合わせて法要を行います。
●十三回忌
十三回忌は、故人が亡くなってから12年後の祥月命日に行います。
十三回忌は七回忌からさらに年数が経過するため、遺族のみで法要を行うことが一般的です。
また、十三回忌以降は年忌法要の省略を行うケースも多くなります。
●十七回忌
十七回忌は、故人が亡くなってから16年後の祥月命日に行います。
十七回忌はほとんどの場合、遺族のみで法要を行うことになるでしょう。
十七回忌は多くの宗派で節目の年と考えられていて、年忌法要を早めに終わらせたいときは十七回忌で弔い上げとすることもあります。
●二十三回忌・二十五回忌・二十七回忌
故人が亡くなってから二十三回忌は22年後、二十五回忌は24年後、二十七回忌は26年後に行う年忌法要です。
3種類の法要をすべて行う必要はなく、宗派によってどの法要を行うかは異なります。3つの法要をすべて省略するという選択肢もあるでしょう。
●三十三回忌
三十三回忌は、故人が亡くなってから32年後の祥月命日に行います。
十三仏信仰では三十三回忌が最後の裁きとされているため、三十三回忌をもって弔い上げとすることが一般的です。
三十三回忌での弔い上げは盛大に法要を行うことが多いものの、近年は小規模な法要に留めるケースも見られます。
●五十回忌
五十回忌は、故人が亡くなってから49年後の祥月命日に行う年忌法要です。
仏教では、死後50年が経つとほとんどの魂は安らかに眠ると考えられていて、三十三回忌ではなく五十回忌を弔い上げとするケースもあります。
まとめ
年忌法要は節目となる年の祥月命日に行う追善供養であり、主な種類としては没後1年目の一周忌から49年目の五十回忌までがあります。
年忌法要をいつまで行うかは宗派・地域によって異なるものの、一般的な弔い上げのタイミングは「三十三回忌」です。ただし、近年は七回忌あたりから法要を省略する、もしくは弔い上げとする家庭も増えています。
年忌法要をいつまで行うかで悩んでいる方は、七回忌から三十三回忌までを弔い上げのタイミングと考えて、家族・親族とも相談して決めるとよいでしょう。