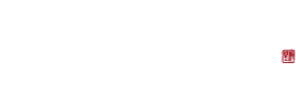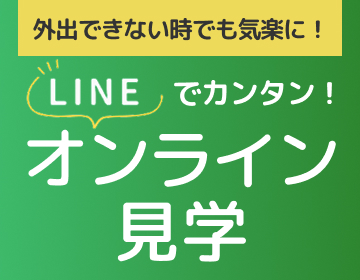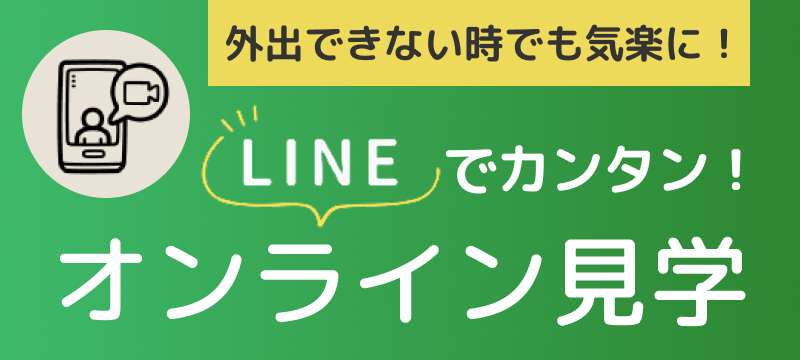生前葬とは?メリット・デメリットや気になるマナーを徹底紹介!

この記事を書いた人
葬儀スタイルが多様化する近年、新たな葬儀の形として「生前葬」が注目を集めています。
生前葬は、本人が存命中に自らの意思で葬儀を行い、家族や親しい人々に感謝の気持ちを伝える新しいスタイルのセレモニーです。人生の節目を自分らしく祝う手段として、多くの人に選ばれつつあります。
生前葬には本人だけでなく家族にとってもメリットがある一方で、注意すべき点もいくつかあります。そのため、生前葬を計画する際はメリット・デメリットを理解し、適切なマナーを押さえて進めることが重要です。
そこで今回は、生前葬の概要やメリット・デメリット、さらに主催者・参列者側がおさえておきたいマナーについて詳しく紹介します。
目次
1. 生前葬とは?

生前葬とは、本人が存命中に自らの意思で葬儀を行い、お世話になった家族や親しい人々に感謝の気持ちを伝えてお別れの時間をもつセレモニーのことです。
従来の葬儀とは異なり、本人が主体となって形式や内容を自由に決められるのが特徴で、会食や挨拶、写真や映像による人生の振り返りなど、参加者とともに和やかな時間を過ごせる内容が中心となっています。
近年では、高齢の有名人やタレントが生前葬を行った事例がニュースなどで報道されることも増え、一般の人々にも生前葬の存在や意味が広く認知されるようになっています。
病気や加齢などで体調や時間に制約があり、元気なうちに親しい人やお世話になった人へ感謝の気持ちを直接伝えたいと考える方や、定年退職や長寿祝いなど人生におけるさまざまなタイミングで自分の想いを周囲に伝えておきたい方にぴったりな、新たなセレモニーの形と言えるでしょう。
1-1. 生前葬とお別れ会の違い
生前葬と混同されやすいものとして、「お別れ会」があります。
お別れ会とは、家族・親族のみで葬儀・火葬を行った後、日を改めてから故人と縁のある人々を招いて故人を偲ぶ会のことです。
生前葬とお別れ会はいずれも形式の自由度が高く、葬儀や通夜のような厳格な法要ではない点が共通しています。
しかし、生前葬は本人が生きているうちに本人自身が主催して行うのに対し、お別れ会は亡くなった後に遺族や知人が主催者として行われる点が大きな違いです。
2. 生前葬のメリット

生前葬は「本人が主体となって準備を進められる」という特徴から、形式や内容の自由度が高い・準備に十分な時間をかけられる・残される家族の負担を軽減できるというメリットがあります。ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
2-1. 形式や内容を自由に決められる
生前葬の最大の特徴は、葬儀の形式や内容を本人が主体となって自由に決められる点です。
従来の葬儀では宗教儀式や慣習に従う必要がありますが、生前葬では会食や挨拶、写真や映像での人生振り返りなど、参加者と一緒に和やかに時間を過ごせる内容を自分の希望に沿って設定できます。
人生の節目や感謝の気持ちを表現する手段として自分らしい形式を選べる点は、非常に大きな魅力となるでしょう。
2-2. 準備に時間をかけられる
生前葬は本人が元気なうちに計画を進められるため、準備や打ち合わせに納得のいくまで十分な時間をかけられる点もメリットです。
時間的な制約はほとんどなく、参加者の選定や会場、演出の内容などをじっくり検討でき、慌ただしい中で決める必要がありません。細部まで自分の意向を反映できることで、より満足度の高いセレモニーを実現できるでしょう。
2-3. 残される家族の負担を軽減させられる
一般的な葬儀では、本人が亡くなった後に家族が葬儀社との打ち合わせや会場・料理の手配などを行う必要があります。しかし、生前葬は基本的に本人自身が準備や手配を行うため、家族が負担を負うことはほとんどありません。
なお、生前葬を行ったからといって葬儀が不要になるわけではありません。しかし、すでに生前葬を行っていたことから、亡くなった後の葬儀はある程度簡略化でき、家族葬など近親者のみでの執り行いも選択しやすくなります。
結果として、家族は落ち着いて故人を偲ぶ時間をもてるほか、経済的・精神的負担を抑えられることにもつながります。
3. 生前葬のデメリット

生前葬は多くのメリットがある一方で、費用や周囲からの理解・協力に関する注意すべき点もいくつか存在します。こうしたデメリットも事前に把握しておくことで、生前葬で起こり得るトラブルを避けやすくなるでしょう。
ここからは、生前葬を行うときの注意点とも言える主なデメリットを2つ紹介します。
3-1. 費用がかかる
生前葬を行うには、当然費用がかかります。どれくらいの費用がかかるのかは規模や内容によって大きく変動しますが、目安として30人~50人程度の小規模な生前葬でも30万円前後は必要と言われています。
場合によっては、自分の死後に残される家族に経済的な負担をかけてしまう可能性もあるため、予算の検討が重要です。
3-2. 周囲の理解・協力を得られにくい
生前葬は必ずしも行う必要はなく、実際に行っていない人の方が多いのが現状です。まだ広く浸透しているとは言えない状況であり、かつ「葬儀は亡くなった後に行うもの」という価値観をもつ方も多いため、周囲の理解や協力を得にくいことがあります。
また前述の通り、生前葬を行ったからといって亡くなった後の葬儀が不要になるわけではありません。生前葬も亡くなった後の葬儀も行うことで、場合によっては家族にとっての時間的・経済的負担がむしろ増す可能性もあります。
そのため、生前葬を行うかどうかは本人の希望だけで進めず、事前に家族とよく相談し双方が納得できる範囲内で決めることが大切です。
4. 【主催者・参列者別】生前葬の気になるマナー

生前葬は厳格なセレモニーではないため比較的自由度が高く、賑やかな時間を過ごせるなど、一般的な葬儀と異なるポイントが多い点が特徴です。そのため、主催者側も参列者側もマナーについてはよく分からず、戸惑ってしまう方も多くいるでしょう。
そこで最後に、生前葬の気になるマナーを主催者側・参列者別に整理して紹介します。
4-1. 主催者側が気を付けるべきマナー
主催者側が気を付けるべきマナーには、下記のようなものが挙げられます。
開催趣旨や日時・場所、服装の指定(平服可など)、会費や香典の有無を明確に伝えることで、参加者が迷わず参加しやすくなります。
● 参加者への配慮
宗教的な儀式の有無や進行内容を事前に明示し、誰もが参加しやすい雰囲気を作ることが大切です。
● 会費・返礼品の準備
香典を辞退する場合は会費制にすることが多く、その際は返礼品を用意しておくと、参加者に感謝の気持ちを伝えやすくなります。
4-2. 参列者側が気を付けるべきマナー
参列者側が気を付けるべきマナーとしては、下記が挙げられます。
案内に従った服装で参列しましょう。平服が指定されている場合は、派手すぎず落ち着いた装いを心がけることが望ましいです。
● 香典・贈り物
主催側の案内(会費制や香典辞退)に従うことが基本です。手ぶらでも問題ありませんが、何か渡したい場合は花やメッセージカードなどが適しています。
● 言葉遣い
本人が健在であるため、「ご冥福」「成仏」など死後を連想させる表現は避けます。「これからもお元気で」「今後ますますのご活躍を」など、前向きな言葉を用いることが好ましいです。
● 写真撮影の配慮
撮影は許可がある場合のみ行い、SNS等への投稿は控えるのが無難です。
まとめ
生前葬は、本人が存命中に自らの意思で行う葬儀で、お世話になった人々へ感謝の気持ちを伝えながら参加者とともに賑やかに過ごせる点が魅力です。
形式や内容の自由度が高く準備に時間をかけられるほか、残される家族の負担を軽減させられる一方で、開催には費用がかかる点や周囲の理解を得にくい点には注意が必要です。
その他、葬儀の生前予約という方法もありますが、こちらは別の回でご説明いたします。
瑞華院 了聞は、東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩3分の場所に位置する全参拝室完全個室、全プラン永代供養付きの室内墓苑(納骨堂)です。終活の一環として、生前葬のほか納骨や永代供養も検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。