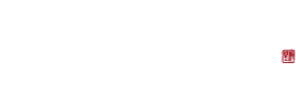ペットの49日(四十九日)とは?数え方から過ごし方まで

この記事を書いた人
近年では大切な家族の一員としてペットと暮らす方も多く、ペットが亡くなった後に葬儀や法要を行う家庭も増えてきました。特に亡くなってから49日目の法要である「四十九日法要」は仏教における重要な節目の1つであることから、人間の場合と同様に丁寧に執り行う家庭も珍しくありません。
そこで今回は、ペットの四十九日法要についての概要や必要性を踏まえた上で、四十九日の数え方や四十九日法要までの過ごし方について解説します。四十九日法要で行うことや服装・持ち物についても併せて確認し、かけがえのない存在であったペットを心穏やかに送り出せるよう準備しましょう。
目次
1. ペットの四十九日法要とは?してあげるべき?

四十九日法要は、亡くなってから49日目に行われる法要のことです。この日は仏教において故人の来世での生き方が決定する重要な日であるとされており、現世に留まっていた故人の魂が死後の世界へと旅立つ日とも言われています。そのため、人間の場合は僧侶の読経や納骨、遺族・親族での会食などを伴う四十九日法要を行うことが一般的です。
ペットの場合、四十九日法要を行う決まりはありませんが、ペットを亡くした悲しみに一区切りをつけるという意味で四十九日法要を行う飼い主も多くいます。形式にとらわれすぎず、そのときの家庭の状況も考慮しながら、自分たちらしい方法で四十九日を迎えることが大切です。
2. ペットの四十九日の数え方
仏教においては、ペットの四十九日も人間の場合と同様に、亡くなった日を1日目として数えて49日目となります。たとえば、ペットが「4月1日」に亡くなった場合は4月1日を1日目として数え始めるため、49日目にあたる「5月19日」が四十九日にあたります。
ただし、最近では四十九日にあたる日に近い休日に四十九日法要を執り行うケースも少なくありません。必ずしも49日目の当日に実施しなければならないわけではないため、自身や家族の予定なども考慮しながら四十九日法要を行う日を決めましょう。
3. ペットが亡くなってから四十九日を迎えるまでの過ごし方

家族として一緒に過ごしてきたペットが亡くなると、深い悲しみや喪失感を抱く方も少なくありません。しかし、このような状況のなかでもペットを見送るために「やるべきこと」がいくつかあります。
ここでは、ペットが亡くなってから四十九日を迎えるまでの過ごし方について解説します。少しずつ心の整理をしていくためにも、主な流れを確認しておきましょう。
3-1. お通夜
人間の場合と同様に、ペットが亡くなった直後に「お通夜」を行う家庭も珍しくありません。基本的には自宅で行うこととなるため、必要なものの準備を忘れないようにしましょう。
遺体は時間が経つにつれて腐敗が進んでしまうため、まずは適切な処置を行うことが大切です。亡くなったペットをきれいに拭いてあげて姿勢を整え、保冷剤やバスタオルを置いた棺の中に優しく寝かせてあげましょう。
ペットの写真や愛用していたおもちゃ、お供えの花やろうそく、線香などを用意して祭壇をつくり、お通夜に参列してほしい親族や友人に連絡をします。お通夜はペットとの最期の別れとなるため、悔いが残らないよう愛情や感謝の気持ちをたくさん伝えてください。
3-2. 火葬・葬儀
ペットの遺体は自宅の庭など自身の所有地であれば土葬することも可能ですが、火葬する場合は火葬業者に依頼する必要があります。火葬の内容や費用は業者やプランによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
火葬後は遺骨をそのままペット霊園などに納骨することもできますが、四十九日法要を行う場合は一度自宅に持ち帰り、祭壇に安置しておくとよいでしょう。祭壇にはできるだけ毎日お線香や大好きだったご飯・おやつをお供えし、亡くなったペットに思いを寄せる時間を設けることをおすすめします。
3-3. 各種法要
お通夜・葬儀が終わったら、四十九日法要までの法要を行うかどうか検討します。仏教においては、亡くなってから49日目までは亡くなった方の魂が成仏していないとされるため、49日目までは命日から7日おきに法要を行うことも可能です。
法要は何日目の忌日であるかによって呼び方が異なるため、四十九日法要までの各種法要を確認しておきましょう。
| 法要の種類 | 概要 |
|---|---|
| 初七日(しょなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて7日目の法要です。近年では葬儀とまとめて初七日法要を行うケースも増えています。 |
| 二七日(ふたなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて14日目の法要です。 |
| 三七日(みなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて21日目の法要です。 |
| 四七日(よなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて28日目の法要です。 |
| 五七日(いつなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて35日目の法要です。五七日を忌明け日とする地域もあります。 |
| 六七日(むなのか) | 亡くなった日を1日目と数えて42日目の法要です。 |
なお、これらの法要をすべて行う必要はありません。しかし、仏教において初七日法要と四十九日法要は特に重要とされる法要であることを押さえておきましょう。
4. ペットの四十九日法要にすること

ペットの四十九日法要は人間と同様の形式で行いますが、ペットの場合は「これをしなければならない」という決まりは特にありません。人間の場合と同じ工程を正確に実施する必要はないため、自身や家族の状況を考慮した上で何を行うか考えてみましょう。
ここでは、ペットにおける一般的な四十九日法要の流れについて説明します。基本的な流れを参考にしながら、四十九日法要で行いたいことやスケジュールを検討してください。
4-1. お経を読んでもらう
ペットの四十九日法要では、人間の場合と同様に僧侶を招いてお経を読んでもらう家庭も多く見られます。ペット霊園やペットも納骨できる寺院・納骨堂などを利用する場合は、その施設・寺院の僧侶に読経を依頼してもよいでしょう。
なお、僧侶を自宅に招いて読経してもらうことも可能です。僧侶のスケジュールを確認する必要があるため、希望する場合は早めに僧侶に連絡することをおすすめします。
4-2. お墓参り・お供えをする
「葬儀後すぐに遺体をお墓に埋葬した」「火葬後すぐにペット霊園や納骨堂などに遺骨を納めた」というケースでは、四十九日法要でお墓参りに行くのがおすすめです。お墓や納骨場所でペットをゆっくりと偲ぶ時間を設けるとよいでしょう。
なお、施設によってはお供え物ができない場合や、お供えできるものの種類が限定されている場合があります。施設側に事前に確認した上でお墓参りの準備を行ってください。
自宅に遺骨を安置している場合は、線香をあげて仏壇にお供え物をします。ペットが生前好きだったご飯やおやつ、おもちゃなどをお供えし、ペットとの思い出を振り返りながら気持ちの整理をしていきましょう。
4-3. 納骨をする
ペットの場合は納骨のタイミングを飼い主が自由に決められるため、必ずしも四十九日法要で納骨する必要はありません。しかし、心に一区切りをつけて飼い主自身が前を向くために、四十九日法要のタイミングで納骨することを決断する家庭も多く見られます。
ペットの納骨方法にはペット霊園や納骨堂に納めるほか、骨壺を自宅で保管する「手元供養」や遺骨の一部をアクセサリーに加工する「メモリアルジュエリー」などもあります。家族で話し合い、納骨や供養の方法を決めておきましょう。
5. ペットの四十九日法要の服装と持ち物

ペットの場合は法要の際に喪服を着用する決まりはありません。たとえば、家族や親しい友人と自宅で四十九日法要を行う場合は私服でも差し支えないでしょう。しかし、人間の納骨施設と併設されている施設やペット霊園など他の家庭のペットも納骨されている施設の場合は、黒など落ち着いた色・デザインの服装を選ぶと安心です。
持ち物についても決まりはありませんが、次のようなものを用意しておくとよいでしょう。
【ペットの四十九日法要での持ち物】
● ペットの写真(遺影)
● お供え物(好きだったおやつやおもちゃ、お花、線香など)
● ハンカチ
なお、人間の場合はお供えの花としてユリや菊、白い花を選ぶケースが一般的ですが、ペットの場合は特に決まりはありません。亡くなったペットに合う色・種類のお花を選んで供えてあげましょう。
まとめ
ペットの四十九日法要は必ず行わなければならない儀式ではありませんが、亡くなったペットに対して深い愛情と感謝を伝える大切な機会でもあります。ペットを失った深い悲しみのなかで、お通夜や葬儀、各種法要の準備を進めることは大変なことではありますが、家族の状況を考慮しながら供養の方法を検討しましょう。
ペットの四十九日法要では僧侶による読経や、お墓・仏壇へのお供え、納骨などが行われることが一般的です。人間の場合と比べて決まり事は少ないため、それぞれの家庭に合った方法で大切なペットを見送ってあげるとよいでしょう。