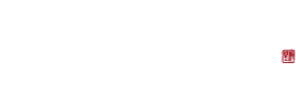ペットにも初七日はある?法要までの流れと供養方法を紹介

この記事を書いた人
ペットは大切な家族の一員であり、亡くなったときには人間と同じように供養したいと考えている方も珍しくありません。人間の場合は亡くなってから7日目に「初七日」の法要を行いますが、ペットでも同様に行うべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ペットの初七日法要を行う意味や必要性、初七日までの流れや過ごし方について解説します。ペットの初七日法要で行うことや初七日以降の主な法要についても併せて確認し、大切なペットの供養をしっかり行いましょう。
目次
1. ペットにも初七日はある?

ペットの初七日とは、ペットが亡くなった日を1日として数えて7日目に行う法要のことを指します。4月1日にペットが亡くなった場合は、7日目の4月7日が初七日法要を行う日となることを押さえておきましょう。
初七日法要は人間が亡くなった場合でも同様に行われる大切な供養の機会であり、亡くなったペットの魂が「三途の川」に到着する日であるとされています。仏教では亡くなってから49日間は魂が成仏せず現世に留まっていると考えられることから、初七日は死後の新しい世界へ旅立つための準備をする時期とも捉えられるでしょう。
初七日法要は必ずしも行う必要はなく、飼い主の判断で実施するかどうかを決定して差し支えありません。しかし、初七日法要を行うことで家族の一員であったペットを偲ぶ時間を設けることができるため、家族との喪失感の共有や自分自身の心の整理がしやすくなります。亡くなったペットへの感謝の気持ちを伝えるよい機会にもなるでしょう。
なお、ペットが亡くなった場合も人間が亡くなった場合と同様に、実際の初七日(亡くなってから7日目)の法要を省略することが可能です。通夜や葬儀と同じ日に初七日法要を行うケースも多いことを押さえておきましょう。
2. ペットの初七日までの流れと過ごし方

家族の一員として一緒に過ごしてきたペットが亡くなると、深い悲しみから今後の供養をどのように進めていくか判断に迷う方も少なくありません。
ここでは、ペットが亡くなってから初七日までの主な流れと過ごし方について解説します。大切なペットのためにしてあげられることを、事前に十分確認しておきましょう。
2-1. 永眠
ペットが亡くなったら、まず遺体のケアを行います。タオルや毛布などの上にペットの遺体を寝かせ、死後硬直が始まる前に優しく手足を折り曲げ、棺に納めやすい体勢にしてあげましょう。まぶたが開いている場合は、手で優しく閉じてください。
次に、濡らしたタオルなどで体をきれいに拭いて清めます。遺体はしばらく自宅で安置することになるため、保冷材やドライアイスを使って体を冷やし、遺体の腐敗を遅らせましょう。時間が経つと体液が流出する場合があるため、耳や鼻、肛門に綿・ガーゼを優しく詰めておくと安心です。
なお、火葬する場合は葬儀会社への連絡も忘れずに行いましょう。
2-2. 通夜
ペットの葬儀は、亡くなった翌日以降に行われることが一般的です。亡くなった当日は自宅でペットの遺体を棺に納めて安置し、最期のお別れとなる通夜を行いましょう。なお、ペット用の棺を準備できなかった場合は、ダンボール箱などで代用しても問題ありません。
通夜は、ペットが亡くなったことを受け入れ、家族と悲しみを分かち合うための大切な時間でもあります。お花やお線香をあげたり、好きなおもちゃや食べ物を棺の近くに置いてあげたりするなど、それぞれの方法でペットとの別れの時間を過ごしましょう。
2-3. 葬儀
葬儀会社やペット霊園など、葬儀を予約した業者のアドバイスを受けながらペットの葬儀を行います。僧侶による読経や焼香が終わったら、火葬または自宅の庭などへの埋葬を行いましょう。
火葬の場合は遺骨を引き取ることになりますが、そのままペット霊園などに納骨することも可能です。自宅に持ち帰り、初七日法要や四十九日法要などで納骨するのもよいでしょう。
3. ペットの初七日法要では何をする?

ペットの初七日法要は家族でペットを偲び、冥福を祈る儀式であり、悲しみと向き合って気持ちを整理する機会でもあります。ペットの初七日法要には細かなルールはないため、飼い主の気持ちや状況に応じて供養をしてあげましょう。
ここでは、ペットの初七日法要で行われることが多い供養方法を3つ解説します。
3-1. 納骨
葬儀の際に納骨をしていない場合は、初七日法要のタイミングで納骨するのも1つの方法です。ペットの遺骨を納める時期に明確な決まりはないため、家族の気持ちに整理がついたタイミングで納骨するとよいでしょう。初七日法要で納骨しない場合は、四十九日法要や一周忌で納骨しても差し支えありません。
火葬後にすぐ納骨した場合や葬儀後に遺体をすぐ埋葬した場合は、お墓や納骨堂などペットが眠っている場所にお参りします。供養の方法には自宅供養やペット霊園、納骨堂での供養のほか、樹木葬やメモリアルジュエリーといった選択肢もあるため、自分や家族に合ったものを選びましょう。
3-2. 読経
僧侶による読経は必須というわけではありませんが、ペット霊園や納骨堂に遺骨を納めている場合は、法要の際に僧侶に読経してもらうことが一般的です。毎月決まった日に法要を行う施設も多いため、初七日法要以降はペットの法要に合わせて参列するのもよいでしょう。
また、自宅で供養する場合でも、僧侶を自宅に招いて読経してもらうことが可能です。僧侶の予定や都合を確認し、自宅に来てもらえるよう連絡しておきましょう。
3-3. お供え
お墓や納骨堂、仏壇などに、ペットが好きだったおもちゃや食べ物、お花などを供えることも、ペットを偲ぶ方法の1つです。ペット霊園や納骨堂の場合は施設によって「お供えができない」「お供えできるものが決められている」などのルールがあります。事前に確認した上でルールに沿ってお供えをするようにしてください。
なお、屋外のお墓に食べ物をお供えする場合、そのままの状態で帰宅すると野生動物による被害が発生する恐れがあります。お供えしたものは基本的にすぐ持ち帰るようにしましょう。
4. ペットの初七日以降の主な法要

ペットが亡くなった場合も人間が亡くなった場合と同様に、初七日以降もさまざまな法要を行うタイミングが存在します。
どの法要をどのように実施するかは特に決まりがないため、家族の気持ちや状況、内容などに応じて実施するかどうかを検討するとよいでしょう。
ここでは、初七日法要以降の主な法要を4つ紹介します。
【ペットの初七日以降の主な法要】
| 法要 | 概要 |
|---|---|
| 三十五日忌(小練忌) | ペットが亡くなってから35日目に行う法要です。初七日と同じように省略されることもあります。 |
| 四十九日(大練忌) | ペットが亡くなってから49日目に行う法要です。魂は死後49日を境に成仏するとされているため、一周忌までの法要の中でも重要な法要であると言えるでしょう。また、四十九日法要で納骨するケースも多く見られます。 |
| 百か日 | ペットが亡くなってから100日目に行います。「ペットが亡くなった悲しみを乗り越える」という意味をもつ法要であり、ペットが亡くなる前の生活に戻るための儀式と言えるでしょう。 |
| 一周忌 | ペットが亡くなってから1年後の命日に行います。四十九日の次に大切な法要であり、一周忌を機に納骨する方も少なくありません。 |
ペットの法要は必ず実施しなければならないものではありませんが、ペットに感謝の気持ちを伝え、自分や家族の気持ちの整理をつけるよい機会にもなります。それぞれの家庭に合った方法で供養を行い、大切なペットの成仏を祈るとよいでしょう。
まとめ
ペットの法要にも「初七日法要」はありますが、通夜や葬儀と一緒に行うケースも多く見られます。亡くなってすぐは遺体のケアや葬儀・火葬の手配などで忙しい場合も多いため、初七日法要を行うかどうかは事前にある程度考えておくとよいでしょう。
初七日法要を行う場合、必要に応じて納骨や僧侶による読経を行い、お墓や納骨堂などにお供えをします。初七日法要以降も四十九日法要や一周忌などペットを偲ぶ機会があるため、それぞれの家庭に合った供養を行うことをおすすめします。