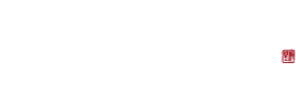【例文付き】訃報の書き方|連絡の範囲・タイミング・内容も解説!

この記事を書いた人
家族や親族が亡くなった場合、関係者に向けて訃報を知らせる必要があります。
しかし、初めて訃報を流す場合、「タイミングはいつか」「何を記載すればいいのか」など不安に感じる方も少なくありません。近い将来、訃報を流す可能性がある方は、連絡の範囲やタイミングなど正式なマナーをチェックしておきましょう。
今回は、訃報の連絡手段と範囲、記載すべき内容と書き方について解説します。訃報の例文と注意事項も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
1. そもそも「訃報」とは?

訃報(ふほう)とは、家族や親族が亡くなった事実を知人や関係者に知らせることを意味します。「訃」という漢字には「人の死を知らせる」という意味があり、訃報は誰かが亡くなった場合にのみ使われる言葉です。
訃報を流すべき主な相手は、下記の通りです。
● 家族や親族
● お寺
● 葬儀会社
● 故人の仕事関係者
● 故人の友人や知人
● 喪主の仕事関係者
訃報は、故人が亡くなった日時や葬儀に関する情報を正しく伝える必要があるため、対応は基本的に喪主が行います。
1-1. 訃報の主な連絡手段
かつての訃報は、新聞・電報・回覧板などを用いて行われていました。現在は、電話やメール、LINEなどのコミュニケーションアプリで訃報を流すケースが増えています。
訃報の連絡手段は、相手によって使い分けることが大切です。親族や近しい知人、高齢の方や上の立場にあたる方に対しては、電話で伝えるのが最善です。相手によってはメールやコミュニケーションアプリによる訃報連絡が失礼にあたる可能性もあるため注意しましょう。
2. 訃報の連絡をすべき関係者の範囲とタイミング

訃報の連絡は、手当たり次第に流せばいいというわけではありません。葬儀を滞りなく行うためにも、連絡すべき範囲とタイミングをしっかり確認しておきましょう。
以下では、訃報の連絡をすべき関係者の範囲とタイミングを解説します。
2-1. (1)家族・親族
個人の兄弟や孫など関係が深い家族や親族に優先的に連絡をして、次に叔父や叔母、いとこなど三等親あたりまでの親族に訃報を流します。
通夜や葬儀などの日時が具体的に決まっていなくても、まずは亡くなった旨を簡潔に伝えましょう。家族・親族への訃報の連絡は、亡くなった直後にできるだけ早いタイミングで行います。
2-2. (2)お寺・葬儀会社
病院で亡くなった場合、葬儀会社に連絡をして自宅や葬儀社の安置室まで搬送してもらうのが一般的です。遺体の安置が終わった後も、通夜・葬儀の打ち合わせや火葬場の手配など葬儀全般のサポートをしてくれます。
菩提寺がある場合は、住職によるお通夜前の枕経が行われます。遺体の安置が終わり次第、お寺にも早めに連絡をしましょう。
2-3. (3)故人の仕事関係者
故人が現役で働いていた場合は、仕事関係者へなるべく速やかに連絡をします。所属部署が分かれば部署の上長へ直接連絡し、分からなければ総務部や人事部に連絡して訃報を伝えましょう。
「故人が経営者の立場である」「直近で重要な仕事があった」など、状況によってはお寺や葬儀会社、付き合いの薄い親族よりも先に故人の仕事関係者へ連絡したほうが良い場合もあります。
2-4. (4)故人の友人・知人
親族・葬儀会社などへの連絡が終わったら、故人が生前親しかった友人や知人にも訃報の連絡をします。通夜・葬儀の場所や日程が決まっていれば、併せて伝えておきましょう。
家族葬で見送る場合は、参列者を限定するために訃報を流す範囲を最低限にとどめるのが一般的です。葬儀が終わってから訃報を伝える場合は、葬儀後1~2週間以内を目安に連絡します。
2-5. (5)自身の仕事関係者
自身の仕事関係者にも身内が亡くなったことを伝える必要があります。さまざまな手続きのためにまとまった休みを取ることになるため、直属の上司にはできるだけ早く一報を入れましょう。
通夜・葬儀の日程が決まったら改めて連絡します。家族葬の場合は、葬儀の形式や香典・弔電の扱いについて事前に伝えておきましょう。
3. 訃報の連絡に記載すべき内容

訃報の連絡では、故人の情報と通夜・葬儀に関する内容などを伝える必要があります。
関係者に書面で訃報を伝える場合に入れておくべき内容は、以下の通りです。
●故人の名前
まずは故人の名前を記載します。年齢は必ず伝えなければならないというわけではありませんが、通夜や葬儀で関係者に尋ねられることもあるため確認しておくとスムーズです。
●亡くなった日時・死因
いつ亡くなったのかが分かるように、亡くなった日付を和暦で記載します。電話で連絡する場合は、「今朝方」「昨夜」などの伝え方でも問題ありません。死因は必ずしも伝える必要はないため、状況に応じて判断しましょう。
●通夜や葬儀の場所・日程
一般葬の場合は、通夜や葬儀を行う場所と日程を記載します。斎場の名称・住所・電話番号・最寄り駅を記載しておくと参列者が足を運びやすくなります。家族葬の場合は、斎場の情報は省略しても問題ありません。
●葬儀の形式(宗旨・宗派)
仏教以外の葬儀を行う場合は、宗旨・宗派を記載します。家族葬は参列者を限定する必要があるため、一般の方の参列を辞退する旨を失礼のないように明記しましょう。
●喪主の名前・連絡先
最後に、喪主の名前と故人との続柄、連絡先を記載します。つながりやすい携帯電話の番号を記載しておくと、訃報を受けた関係者との連絡がスムーズです。
香典・供花・供物を辞退する場合は、訃報を連絡する段階で伝えておきます。「勝手ながら故人の遺志により辞退させていただきます」のように、失礼のない文面を心がけましょう。
4. 訃報の書き方と例文
書面で訃報の連絡をする場合は、例文を参考に必要な情報をまとめましょう。
親族・友人・知人に対して書面で訃報を伝える場合の書き方と例文は、以下の通りです。
【親族・友人・知人宛の訃報例】
かねてより闘病しておりました父〇〇が 令和〇年〇月〇日に永眠いたしました
生前は多大なご懇親を賜り誠にありがとうございました
なお 通夜は近親者で済ませた後 告別式は下記の通り仏式にて執り行います
記
1. 日時 告別式 令和〇年〇月〇日 午前〇時から〇時
2. 式場 〇〇〇(斎場の名称・住所・電話番号)
3. 喪主 〇〇(長男) 連絡先:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
書面で訃報を連絡する場合は、句読点を省略します。必要な情報が相手に伝わるように、簡潔に記載するのがポイントです。
訃報には、「くれぐれも」「また」「たびたび」などの重ね言葉や、苦しみを連想する「苦」「死」などは使わないのがマナーです。「大変」「4」「9」など不吉とされる言葉や数字にも注意しましょう。
家族が亡くなったことを自身の仕事関係者に伝える場合の書き方と例文は、以下の通りです。
【会社関係者向けの訃報例】
〇〇部 〇〇様
令和〇年〇年〇月〇日、かねてより闘病しておりました父が他界いたしました。
下記、ご報告申し上げます。
記
死亡者氏名:〇〇(享年75歳)
続柄:実父
死亡日:令和〇年〇月〇日
通夜・葬儀は親族のみで執り行う予定です。
葬儀へのご参列、ご香典などのご厚志につきましては、失礼ながら辞退させていただきます。
なお、〇月〇日~〇月〇日の〇日間、慶弔休暇を申請させていただきます。
〇〇部〇〇課 〇〇(自身の名前)
休暇中の連絡先:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メールでの訃報は略式であるため、句読点を記載しても問題ありません。ただし、重ね言葉や忌み言葉の使用は避けましょう。
まとめ
訃報の連絡手段は、電話・メール・コミュニケーションアプリが主流です。ただし、高齢の方や年配の方への連絡の場合、メールやコミュニケーションアプリは失礼にあたることがあるため、電話で行うのが無難です。
訃報の連絡は、家族・親族・葬儀会社への連絡を優先します。故人が現役で働いていた場合は、仕事関係者にも速やかに連絡が必要です。
訃報の連絡では、故人の名前・亡くなった日時・通夜や葬儀の日程などを簡潔に伝えます。家族が亡くなったことを自身の仕事関係者に伝える場合は、慶弔休暇の申請についても併せて記載しましょう。