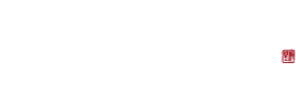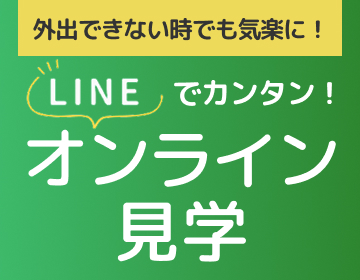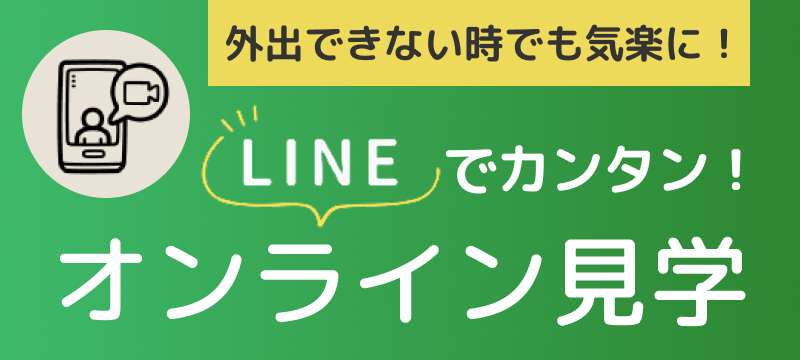法事とは?種類・タイミングから必要な準備と流れまで徹底紹介!

この記事を書いた人
大切な人が亡くなった後、故人を供養するために親族・縁者が主体となって執り行うのが「法事」です。しかし、「いつ、どのように行えばよいのか」「何を準備すればよいのか」など、具体的な時期や流れが分からず不安に感じる人も多いでしょう。
法事には、亡くなってから一定の期間ごとに行う「忌日法要」と、年単位で執り行う「年忌法要」の2種類があります。今回は、各法要の違いやタイミングを分かりやすく解説します。法事をスムーズに進めるための参考にしてください。
1. 法事とは?

法事とは、仏教の行事の1つです。故人を供養するために僧侶が読経し、親族や故人とゆかりのある人々が集まる機会を指します。仏教では死後の世界や輪廻転生の考えがあり、故人がよりよい世界へ導かれるよう祈ることが主な目的です。
法事には、忌日法要や年忌法要などの供養に加え、お盆や彼岸供養といった仏教行事も含まれます。遺族や参列者にとっては故人の冥福を願いながら、ともに在った日々の思い出を振り返る大切な機会です。また、僧侶の説法を通じて仏教の教えを学ぶ場でもあります。
法事では、法要後に僧侶や参列者を招き「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を行うのが一般的です。ともに食事をすることで、親族や参列者の親睦を深める意味も持ちます。
1-1. 法事と法要の違い
「法事」と「法要」は意味も音も似ており、混同されがちな言葉ですが、厳密には異なる意味を持ちます。法要は僧侶の読経や焼香など、故人の魂を供養する宗教的な儀式そのものを指す言葉です。一方、法事は法要に加え、その後の会食なども含めた行事全般を指します。
日常会話では、法要を「法事」と呼ぶこともあるものの、本来、法要は法事の一部です。使い方を間違えても大きな問題になることはほぼありませんが、正しい意味合いを理解しておくとよいでしょう。
2. 法事の種類とタイミング

法事には大きく分けて「忌日法要」と「年忌法要」の2種類があります。亡くなってから日数を基準に行う法要が忌日法要で、年単位で執り行うのが年忌法要です。
どちらも故人の冥福を祈るための重要な行事ですが、何回目の命日を迎えるかによって法要の名称や意義が変わるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
2-1. 忌日法要
忌日法要とは、故人の命日から七日ごとに行う法要です。仏教では、人が亡くなってから四十九日間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、故人が閻魔大王の審判を受ける期間とされています。そのため、遺族は七日ごとに供養を行い、故人の魂が安らかに成仏できるように祈ります。
忌日法要の種類は、以下の通りです。
| 7日目 | 初七日(しょなのか) |
|---|---|
| 14日目 | 二七日(ふたなのか) |
| 21日目 | 三七日(みなのか) |
| 28日目 | 四七日(よなぬか・ししちにち) |
| 35日目 | 五七日(いつなのか) |
| 42日目 | 六七日(むなのか・むなぬか) |
| 49日目 | 七七日(しちしちにち・なななぬか) |
| 100日目 | 百カ日(ひゃっかにち) |
初七日は、故人が三途の川に到着する日とされており、無事に渡れるよう皆で祈ります。近年では、葬儀当日に初七日法要を繰り上げるケースも少なくありません。
二七日~四七日は、故人の生前の行いについて「盗み」「不貞」「言葉」の順に審判が続く期間です。家族のみで済ませるのが一般的で、省略する家庭が多くなりました。
地域によっては「忌明け」として扱われるのが、五七日です。故人の生前の行いがすべて審判の場に映し出されるとされ、遺族が供養を行うことで、よりよい来世へ進めると考えられています。六七日は、弥勒菩薩が過去の罪について裁きを下す日です。
七七日(四十九日)は、もっとも重要な忌日法要です。閻魔大王の審判が終わり、故人の魂がどのような世界に生まれ変わるかが決まります。この法要をもって「忌明け」となり、喪に服していた遺族が日常生活に戻る節目とするのが一般的です。
百カ日(卒哭忌)は、故人の死を悲しむ時期が終わり、遺族が故人を偲びつつも前を向いて生きていくための法要です。省略されることもありますが、親族が集まり、故人を想いながら供養を行う場となります。
なお、法要の形は家庭や地域の習慣によって異なるため、事前に親族や菩提寺と相談しながら準備を進めることが大切です。
2-2. 年忌法要
年忌法要とは、故人の命日から特定の年数が経過したタイミングで行う追善供養です。亡くなって1年目に行われる「一周忌」、2年目の「三回忌」をはじめ、節目ごとに法要を執り行います。一般的には三十三回忌をもって「弔い上げ」とし、それ以降の法要は行わない場合が多いですが、宗派や地域によって異なります。
年忌法要の種類は、以下の通りです。
● 三回忌
● 七回忌
● 十三回忌
● 十七回忌
● 二十三回忌
● 二十七回忌
● 三十三回忌
● 三十七回忌
● 四十三回忌
● 四十七回忌
● 五十回忌
● 百回忌
一周忌は、故人が亡くなって1年後の命日に行われる最初の年忌法要で、喪が明ける節目とされています。僧侶の読経後に焼香をし、会食を行うのが一般的です。
三回忌は、亡くなってから2年目の命日に行われます。3年目ではない点に注意しましょう。一周忌ほどの規模ではありませんが、親族や故人と縁のあった人が集まることが多い傾向にあります。
七回忌は、亡くなってから6年目に行われる法要で、三回忌よりも規模が小さくなるケースが一般的です。十三回忌は、12年目の命日に行われる法要です。親族のみで執り行われることが多く、読経や焼香の後に会食をする場合もあります。
十七回忌は、亡くなって16年目に行われる法要です。参列者の数も減り、家族のみで行う形が多いものの、故人と親交が深かった方を招くケースも少なくありません。二十三回忌・二十七回忌は、それぞれ22年目と26年目に行われる法要ですが、省略される傾向にあります。
三十三回忌は、32年目の命日に行い、弔い上げとする宗派が多い法要です。個人の位牌を先祖代々の位牌に合祀する場合もあります。四十三回忌・四十七回忌は、執り行う家庭が少なくなり、複数の故人をまとめて供養する場合もあります。
五十回忌は、亡くなって49年目に行われる法要です。三十三回忌で弔い上げをしなかった場合は、ここで実施します。
百回忌は99年目の命日に行われますが、一般家庭では滅多に実施されません。
年忌法要の回数や内容は、家庭の考え方や地域の慣習によって異なります。ただ、近年は三回忌以降は省略する家庭が多く、全般的に簡素化する傾向が強まっています。法要を執り行う際は、親族や菩提寺と相談しながら無理のない範囲で執り行うことが大切です。
3. 【喪主向け】法事に必要な準備と流れ

一般的な法事の準備と流れは、以下の通りです。
| (1) | 会場と日時を決める |
|---|---|
| 命日が平日の場合、参列者が集まりやすい休日に調整する傾向にあります。僧侶の都合も考慮し、早めに決定しましょう。 | |
| (2) | 僧侶へ依頼する |
| 菩提寺がある場合は、直接相談します。ない場合は、葬儀社や僧侶派遣サービスを利用するとよいでしょう。 | |
| (3) | 案内状の送付 |
| 出欠確認を兼ねた案内状を送ります。返信期限を設けるとスムーズです。 | |
| (4) | 会食と引き出物の手配 |
| 法事後の会食を手配し、参列者に合わせた返礼品を準備します。 | |
| (5) | お布施の準備 |
| 僧侶へのお布施、お車代、会食に参加しない場合の御膳料を用意しましょう。 | |
法事を滞りなく進めるためには、事前の準備が重要です。
まとめ
法事とは、仏教の教えに基づいて故人を供養する行事で、僧侶の読経や焼香といった法要に加え、会食を伴う形が一般的です。法事には「忌日法要」と「年忌法要」の2種類があります。忌日法要は故人の命日から七日ごと、年忌法要は一周忌や三回忌など年単位で行う供養です。
法事を行う際は、会場や日時の決定、僧侶や参列者への連絡、会食や引き出物の用意など、さまざまな準備を進めなければなりません。どの法事をどれだけの規模で執り行うかは、各家庭の考え方や地域によっても異なるため、親族でよく話し合って決めましょう。