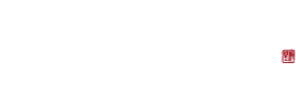法然上人とは?誕生から往生までの歴史と浄土宗の教えについて

この記事を書いた人
法然上人(ほうねんしょうにん)は、日本仏教の代表的な宗派の1つである「浄土宗」の宗祖です。現在も多くの日本人に支持される浄土宗を開いた法然上人は、どのような生涯を送り、浄土宗の教えにつながる悟りを開いたのでしょうか。
当記事では、法然上人がどのような人物であるかをふまえた上で、法然上人の生涯について解説します。法然上人が往生された後に、浄土宗の教えを広め伝える役割を果たしてきた増上寺についても併せて確認し、法然上人と浄土宗の歴史に対する理解を深めましょう。
目次
1. 法然上人(ほうねんしょうにん)とは?

法然上人(ほうねんしょうにん)とは、日本仏教の宗派の1つである浄土宗の宗祖として広く知られる人物です。平安時代末期から鎌倉時代に生きた僧侶であり、「ほかの行をまじえずただ称名念仏をひたすら修することで阿弥陀仏の浄土へ往生できる」という「専修念仏」の教えを説きました。
法然が生きた時代は、貴族の時代から武士の時代への過渡期であり、保元の乱や平治の乱といった戦や大きな地震や飢饉などで人々は非常に厳しい生活を強いられていました。また、時代とともに仏の教えが衰えて乱世になるという「末法思想」も人々に広がっていたと言われています。
このような「末法の世」の中で、専修念仏は庶民を中心に武士や貴族、天皇からも支持されました。法然が開いた浄土宗は鎌倉新仏教の先駆けとなるだけでなく、後の日本仏教にも大きな影響を与え、現在でも広く受け入れられています。
2. 法然上人の生涯

民衆から広く支持される教えを説いた法然上人ですが、その生涯は苦難の連続であったと言われています。法然はどのような幼少期を過ごして仏教と出会い、専修念仏の教えを悟ったのでしょうか。
ここでは、法然の誕生から往生までの波乱に満ちた生涯・歴史について紹介します。
2-1. (1133年~)法然上人の誕生と父の死
法然上人は、平安時代後期にあたる1133(長承2)年に、美作国(現在の岡山県)で生まれました。父親の漆間時国(うるまときくに)は源氏の流れを汲む美作国の豪族であり、犯罪者や謀反人を捕らえることを任務とする押領使です。また、母親は秦氏(はたうじ)と呼ばれていました。
法然は幼名を「勢至丸(せいしまる)」といい、漆間家の後継ぎとして育てられていました。
しかし、勢至丸が9歳の頃、父である時国は対立していた源定明の軍勢から夜襲を受けて亡くなります。時国が勢至丸に遺した「敵を恨んではならない。出家して本当の幸せを求めなさい。」とする言葉は、勢至丸の心に深く刻み込まれ、後の生涯に大きな影響を与えました。
2-2. 仏教との出会い・比叡山での修行開始
父を亡くした勢至丸は、母親の血縁を頼って「菩提寺」という寺へ預けられます。叔父の勧覚という僧侶の下で仏教を学び始めますが、その才能を見出されて15歳の頃に当時の仏教の中心地である比叡山延暦寺へと送り出されました。
比叡山では持宝房源光という僧侶の下で修行を始めます。修行を通じて勢至丸の能力の高さを見出した源光は、天台宗の教えに精通した皇円という僧侶に勢至丸を託すことにしました。
2-3. 出家・法名「法然房源空」の授与
皇円の下に送られた勢至丸は正式に出家し、天台宗の僧侶となりました。皇円は勢至丸の優秀さに驚き、僧侶としての地位を高めて指導者を目指すよう勧めます。しかし、勢至丸が仏教を学ぶ目的は「父の供養」と「本当の幸せを求めるため」でした。勢至丸は初志貫徹のため皇円の下を去り、西塔黒谷の叡空に師事します。
勢至丸の考えに感銘を受けた叡空は、「法然道理(あるがままの自然の姿)」から「法然」、そして最初の師である「源光」と「叡空」から「源空」という名を送りました。これが法然房源空の由来です。
2-4. 比叡山の厳しい修行と悩み
法然上人は叡空の下で厳しい修行に励み、仏教の教えへの理解を深めます。しかし、修行を通してこのように厳しく難解な教えが、争いや自然災害・飢饉などで苦しんでいる人々に本当に適しているのか、疑問を抱くようになりました。
そこで、法然は自身の学びが正しいかどうかを知るために、京都や奈良の寺院に赴いて各宗の僧侶を訪ねます。しかし、いずれも法然が満足する回答は得られず、法然はさらに悩みを深めることになったのです。
2-5. 「観無量寿経疏」との出会い
京都・奈良から比叡山に戻った法然上人は、自身を仏教への理解が乏しい存在「凡夫」であるとし、荒廃した世に生きる人々も等しく凡夫であると考えるようになります。そして、これらの凡夫が救われる教えを探すために、黒谷の報恩蔵にこもってさまざまな経典を一心不乱に読みふけりました。
その中で、法然は唐の時代の僧侶・善導大師が著した『観無量寿経疏(かんむりょうじゅきょうしょ)』に出会います。「一心に阿弥陀仏の名を常に唱え続けることは正定の業であり、それは阿弥陀仏の本願である」とする言葉に触れ、凡夫も念仏によって浄土に往生できることを確信しました。
2-6. 専修念仏の教えの広まり
『観無量寿経疏』に出会った法然上人は比叡山を下り、「南無阿弥陀仏」と一心に念仏を唱えることで誰もが救われる「専修念仏」の教えを人々に広め始めました。
この教えは、厳しい修行や寺社への寄進をする余裕のない庶民に瞬く間に広がり、貴族や武士だけでなく天皇・上皇にまでも受け入れられたのです。
2-7. 大原問答と浄土宗の広まり
法然上人の「専修念仏」の教えは他の僧侶たちにも伝わります。法然の教えについて知りたいと考えた天台宗の僧侶・顕真は、多くの僧侶を招いて比叡山山麓にある大原という地で討論会を開きました。
この討論会において、法然は現世で厳しい修行をして悟りを得る一般的な教えと、念仏で往生してから悟りを目指す浄土宗の教えでは内容に優劣はないとする立場を示しました。一方で、今の時代や人間の能力を考慮すると、浄土宗の教えが合っているとする見解も示しています。
これらの回答に納得した僧侶たちは、法然とともに念仏を唱えたと言われています。この出来事は「大原問答」と呼ばれており、浄土宗の教えが広がるきっかけとなった重要な出来事とされています。
2-8. 元久の法難と建永の法難
法然上人の「専修念仏」の教えが民衆に広まる一方で、教えを誤って理解して他の宗派をおとしめる者も現れました。これにより、浄土宗と他宗の寺院・僧侶との関係が悪化します。
1204(元久元)年、延暦寺の僧侶が念仏の差し止めを自院のトップに求め、法然はその対応のために弟子たちに行いを改めさせる文章を作りました。これが「元久の法難」と呼ばれる出来事です。
しかし、法然が対応したにもかかわらず事態はさらに深刻化し、法然の弟子2人が後鳥羽上皇の侍女を無断で出家させる事件が発生します。
この事件に対して上皇は、浄土宗の信仰が朝廷の秩序を乱すものと見なし、1207(建永2)年には弟子2人に死罪を、法然には「土佐への流罪」を処罰として命じました。
ところが、法然上人の門下で深い信頼関係のあった関白・九条兼実公の恩赦によってその処罰は軽減され、最終的に九条家の荘園があった「讃岐国」への留配が決定しました。この出来事は「建永の法難」と呼ばれています。
2-9. 一枚起請文の執筆と往生(1212年)
建永の法難によって讃岐国へ配流された法然は、その後朝廷から帰京の許しを得て京都に戻りましたが、間もなく病に倒れ、次第に弱っていきました。
そして1212(建暦2)年、法然上人の身の回りの世話をしていた弟子・源智は、法然の往生が近いことを感じ、法然に浄土宗の教えの重要な部分を書きとどめるよう願い出ました。その願いを聞き入れて法然が執筆したのが「一枚起請文」であるとされています。
「一枚起請文」を記したとされる日から2日後の1月25日、最期まで念仏を唱えながら法然は往生を遂げ、浄土へと還りました。
3. 浄土宗と増上寺の発展

法然上人が往生を遂げた後も、浄土宗の教えは広まり続け、さらなる発展を遂げることになります。特に、1393年に創建されたとされる増上寺は江戸幕府・徳川家の菩提寺としても知られており、開創以降、浄土宗の教えを伝える場として中心的な役割を担い続けてきました。
現在の増上寺にも法然上人の精神は受け継がれており、念仏を唱えて阿弥陀仏への浄土往生を願う心が多くの人々に伝えられています。今後も増上寺は浄土宗の歴史をふまえ、僧侶の育成や法然上人の教えの発信など現代社会における新たな役割を果たしていくことが期待されます。
まとめ
法然上人とは、日本仏教の代表的な宗派の1つである「浄土宗」の宗祖であり、専修念仏の教えを説いた人物です。父の死や比叡山での厳しい修行を経て、「阿弥陀仏の浄土へ往生するために、ただひたすら称名念仏を修する」という道に辿りついた法然の生き方と教えは、当時から広く受け入れられ、現在の日本にも深く根付いています。
浄土宗の教えを伝える寺院は数多く存在しますが、特に徳川家の菩提寺でもある増上寺はその中心的な役割を担ってきました。今後も増上寺は法然上人の教えを多くの人々に伝え、現代社会において新たな役割を果たしていくことが期待されます。