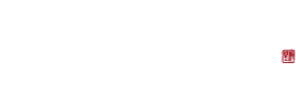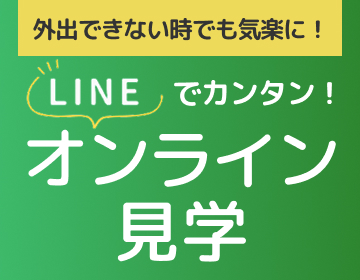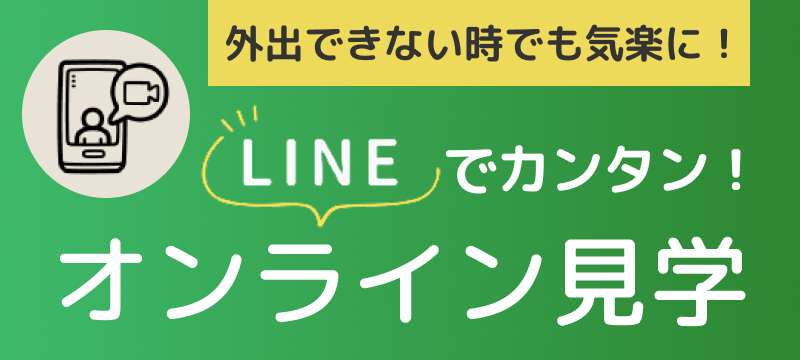御忌会とは?主な法要・儀式の内容や御忌大会を行う代表的な寺院も

この記事を書いた人
浄土宗は「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)の念仏を唱えることで、阿弥陀仏の浄土へ往生できると説く宗派です。他の行をまじえず、ただひたすらに称名念仏を修する「専修念仏」を基本とし、 開宗から約850年が経った現在も多くの人々に信仰されています。
浄土宗寺院で行われる御忌会は開祖・法然上人の忌日法要であり、江戸時代の人々にとっては新年の一大イベントでもありました。現在の御忌会は桜の時期に開催され、俳句の世界では春の季語とされています。
今回は、御忌会の概要とともに特に大規模な御忌大会が行われる寺院について解説します。
目次
1. 御忌会(ぎょきえ)とは?

御忌会とは、浄土宗の開祖である法然上人の忌日法要です。「御忌」はもともと天皇家や皇族や高僧などの法要を指す言葉でしたが、現在では法然上人の法要として、俳句の春の季語としても広く知られています。
法然上人は建暦2年(1212)1月25日に80歳で往生し、その後しばらくは弟子や信徒たちによって「知恩講」と呼ばれる忌日法要が営まれていました。大永3年(1523)には後柏原天皇が京都の知恩院へ勅書を送り、毎年1月18日から25日に法然上人の御忌を行うよう定めました。これが、現在の御忌会の原型と言われています。
江戸時代の民衆にとって、御忌会は新年の大きな楽しみのひとつでした。特に大規模な御忌が行われる知恩院や増上寺は、寒さに震えつつも僧侶や稚児たちの華やかな行列をひと目見ようとする物見遊山客で賑わいました。
明治時代以降、多くの寺院では4月に御忌会を行っています。寒い1月よりも気候のおだやかな4月に法要を営むことで、より多くの人に参拝してもらいやすくするためです。多くの寺院では御忌会の法要を公開しており、信徒はもちろん一般参拝者も法要に参拝したり上人の教えを学んだりすることが可能です。
1-1. 御忌会と御忌大会の違い
一般的に、「御忌会」と「御忌大会(ぎょきだいえ)」はほぼ同じ意味で用いられます。厳密に言うと御忌会は法要そのものであり、御忌大会は全国の浄土宗寺院の僧侶や信徒が集まる大規模な法要です。
現在は全国各地の寺院で御忌会や御忌大会が行われており、なかでも総本山知恩院や東京の大本山増上寺などの御忌大会が特に有名です。
2. 御忌会で行われる主な法要・儀式
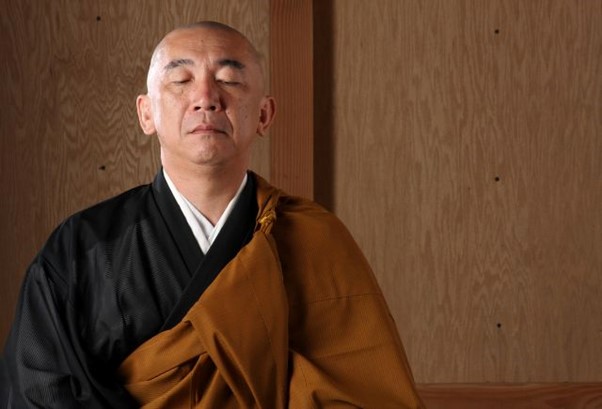
御忌会ではおもに逮夜法要や日中法要と呼ばれる法要が営まれるほか、一般参拝者も楽しめる儀式もしばしば行われます。寺院によって詳細は異なるものの、御忌会におけるおもな法要や儀式の概要はおおむね次の通りです。
2-1. 逮夜法要
逮夜(たいや)とは忌日の前日の夜であり、知恩院などでは日中法要の前日の午後から夜にかけて逮夜法要が営まれます。
知恩院における逮夜法要の大きな見どころは、「笏(しゃく)念仏」と呼ばれる浄土宗ならではの念仏です。笏とは礼服や束帯を着た男性が手にする細長い木の板であり、笏を持つことで姿勢と威儀を正す効果があると言われています。
後柏原天皇からの勅書に笏が添えられていたことにちなみ、笏を打ち鳴らす音に合わせて大勢の僧侶たちが念仏を唱えながら堂内を練り歩きます。念仏とともに雅楽が演奏され、堂内は厳かでありつつも華やかな空気に包まれます。
2-2. 日中法要
その名の通り日中に行われる日中法要では、唱導師が諷誦文(ふじゅもん)を唱えます。諷誦文は法然上人の徳をたたえるとともに法要の趣旨を伝える文であり、独特の節をつけて唱え上げられることが特徴です。浄土宗の僧侶にとって、御忌会で唱導師を務めることはこの上ない名誉とされています。
また、一部の寺院では日中法要と同時に献茶式を行います。献茶式は法然上人にお茶を供えるための儀式ですが、一般参列者向けに茶席を設ける寺院も少なくありません。
2-3. 舞楽奉納
増上寺では、約90年もの歴史を持つ雅楽会会員によって舞楽が奉納されます。会期中は毎日舞楽が上演され、演目は「蘭陵王」や「還城楽」をはじめ日によってさまざまです。さわやかな青空と見ごろを迎えた桜の下で行われる雅楽は、多くの参拝者を惹きつけてやみません。
3. 御忌大会が行われる代表的な寺院とその特色

現在は全国各地の浄土宗寺院で御忌会が行われており、なかには観光スポットとして国内外から多くの参拝者が訪れる寺院も少なくありません。
次に、特に大規模な御忌大会を行う寺院およびそれらの寺院の特色について解説します。
3-1. 大本山 増上寺(東京都)
東京の代表的な観光スポットでもある増上寺は、明徳4年(1393)に浄土宗第八祖の酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人によって創建された寺院です。
江戸時代になると徳川将軍家の菩提寺として手厚く保護され、関東における浄土宗寺院のまとめ役として総本山知恩院に勝るとも劣らない地位を確立しました。
明治維新後の境内地召し上げや戦災などによる苦難もあったものの、3階建ての大殿や秘仏「黒本尊」を奉じる安国殿などが並ぶ境内は多くの参拝者でにぎわっています。
増上寺の御忌大会は、例年4月2日から7日にかけて行われます。日中法要では江戸三大名鐘として知られる大梵鐘が鳴らされ、唱導師や稚児たちが華やかな行列をなして大門から大殿へと練り歩きます。
3-2. 大本山 百萬遍知恩寺(京都府)
百萬遍知恩寺(ひゃくまんべんちおんじ)は、もともと賀茂の神領にあった僧房であり、法然上人の一時的な住まいだったと言われています。上人の往生後この僧房は弟子たちに受け継がれて知恩寺と名づけられ、北白川へ移転しました。現在は「百万遍さん(百萬遍さん)」の愛称で人々に親しまれ、毎月15日に境内で開催される「手づくり市」も人気です。
百萬遍知恩寺法然上人御忌大会は、4月23日から25日ごろに行われます。会期中の3日間は日中法要および逮夜法要が営まれ、また法要と同時に大念珠繰りが行われます。
この大念珠は、悪疫退散を祈願した8世空円上人の功績をたたえるために後醍醐天皇が下賜したものです。また、「百萬遍」の寺号は空円上人が阿弥陀仏の名を百万回唱えて祈願したことに由来しています。
3-3. 浄土宗総本山 知恩院(京都府)
知恩院は、承安5年(1175)に法然上人が現在の御影堂付近に結んだ草庵を起源とする寺院です。現在の広大な伽藍は江戸幕府の援助を受けて形成されたもので、境内には法然上人像が安置されている国宝御影堂をはじめ多数の国宝や重要文化財があります。
また、黒門前路上の瓜生石や左甚五郎の忘れ傘などの「知恩院の七不思議」も有名です。三門前には写経体験などもできる宿泊施設「和順会館」があり、京都観光の拠点として活用する人も少なくありません。
知恩院における御忌大会の会期は、4月18日から25日の8日間です。初日の夜には、国宝山門楼上にて夜通し念仏を唱え続ける「ミッドナイト念仏in御忌」が行われます。日中法要および逮夜法要は御影堂で営まれ、最終日には法要が無事に終わったことを感謝する放生会も行われます。
4. 浄土宗以外の宗派で行われる忌日法要の名称
浄土宗以外の寺院でも、開祖や中興の祖の忌日法要が広く行われています。国内の主な宗派における忌日法要は、次の通りです。
| 宗派 | 名称 | 内容 | 日程 |
|---|---|---|---|
| 浄土真宗 | 報恩講 (ほうおんこう) | 親鸞聖人の忌日法要 | 10月~1月ごろ (宗派により異なる) |
| 真言宗 | 正御影供 (しょうみえく) | 弘法大師(空海)の忌日法要 | 3月21日 |
| 法相宗 | 慈恩会 (じおんね) | 慈恩大師の忌日法要 | 11月13日 |
| 日蓮宗 | 御会式 (おえしき) | 日蓮上人の忌日法要 | 10月13日ごろ |
| 曹洞宗 | 御征忌 (ごしょうき) | 道元禅師、または瑩山禅師(中興の祖)の忌日法要 | 9月中旬~下旬 10月中旬~下旬 |
| 天台宗 | 山家会 (さんげえ) | 伝教大師(最澄)の忌日法要 | 6月4日ごろ |
寺院によっては、これらの忌日法要を一般公開していない場合があります。忌日法要に参拝したい場合は、あらかじめ寺院に確認すると安心です。
まとめ
多くの浄土宗寺院で毎年4月に行われる御忌会は、開祖・法然上人の遺徳をたたえて教えを今に伝えるための忌日法要です。日中法要や逮夜法要で唱えられる独特な節回しの声明は、聴く人をまるで極楽浄土にいるかのような心地にさせてくれます。
観光スポットとしてもおなじみの東京・増上寺や京都・知恩院などでは、特に大規模な御忌大会が行われます。法要とともに参拝者向けの茶席や舞楽奉納なども行われる御忌大会は、信徒はもちろん信徒以外の一般参拝者もおおいに楽しめるでしょう。