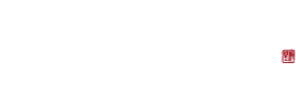墓じまいにかかる費用の相場は?安く抑えるポイントも徹底解説!

この記事を書いた人
近年、少子高齢化や核家族化が進む中で、「後継者がいない」「お墓の管理が難しい」といった理由から、墓じまいを真剣に考える家庭も増えてきました。しかし、その手続きや費用について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
当記事では、墓じまいにかかる費用の相場や内訳、費用負担の選択肢や節約のポイントについて解説します。初めて墓じまいを検討する方でも混乱しないよう、基本的な情報を分かりやすく紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 墓じまいとは?

墓じまいとは、現在利用しているお墓を撤去・解体して更地にし、墓地の使用権を返還する手続きです。この際、元のお墓に納められていた遺骨は、新しい納骨先に移して供養する必要があります。
近年、墓じまいを選択する人が増加しています。主な理由として挙げられるのが、少子高齢化や核家族化の進行です。さらに、無縁墓(管理者がいないお墓)が社会問題として注目されたことも影響しています。
お墓を受け継ぐ後継者がいない方や、子どもに管理の負担をかけたくない方が、元気なうちに墓じまいを行うケースが増えてきました。また、お墓が遠方にある場合、年齢を重ねるにつれお墓参りが困難になるのも、墓じまいを決断する要因の1つです。
2. 墓じまいの費用相場と内訳

墓じまいにかかる費用の相場は約30万円~300万円と幅があります。
費用に幅が生じる理由は、墓石の大きさや撤去場所の条件、新たな納骨先の種類や供養の方法によって、それぞれ費用が異なるためです。たとえば、墓石を1つだけ撤去して手元供養を行う場合は費用を抑えられますが、墓地が山奥だったり新たなお墓を建てたりすると総額が高くなります。
また、墓じまい費用の内訳は、大きく「現在のお墓の撤去費用」「新しい納骨先にかかる費用」「行政手続きにかかる費用」の3つの項目に分けられます。
2-1. 現在のお墓の撤去にかかる費用
墓じまいの第一段階として、現在のお墓の撤去が必要です。この工程では、墓石の撤去・解体や関連する儀式に費用が発生します。各費用の目安は以下の通りです。
| 墓石の撤去費用 | 10万~15万円程度(1平方メートル当たり) |
|---|---|
| 墓石の解体や撤去を行い、墓地を更地にする作業です。お墓の面積や石材の量、重機の使用の可否によって金額が変わります。重機が入らない立地では手作業となり、費用が高額になる場合があります。 | |
| 閉眼供養(お布施) | 3万~10万円程度 |
| お墓から故人の魂を抜き、ただの石に戻す儀式である閉眼供養の費用です。読経を行う僧侶へのお布施が中心となりますが、お寺や地域によって料金設定が異なるため、事前の確認が重要です。 | |
| 離檀料 | 3万~20万円程度 |
| お寺の檀家を離れる際にお渡しする費用です。法要1回分程度が目安とされていますが、地域やお寺によっても請求額に差があります。 | |
撤去工事の費用は、墓地の立地条件や墓石の規模によって大きく異なります。また、お布施や離檀料の金額に不明点がある場合は、事前に寺院に確認しましょう。複数の石材店から見積もりを取り、条件を比較検討することが重要です。
寺院との交渉が難しい場合、地域の石材店や弁護士に相談するのも1つの手段です。
2-2. 新たな納骨先(改葬先)にかかる費用
日本の法律では、故人や先祖のご遺骨を勝手に破棄したり、放置したりすると罪に問われます。そのため、墓じまいをした後、遺骨を供養する新たな場所を用意しなければなりません。
| 新しい納骨先の初期費用 | 数百円~300万円程度 |
|---|---|
| 遺骨を納める新しい場所の費用で、墓地の種類によって価格差があります。 | |
| 開眼供養(お布施) | 3万~30万円程度 |
| 新しい納骨先で故人の魂を入れる儀式です。僧侶に依頼する際のお布施が含まれます。 |
納骨先による費用相場の目安は、以下の通りです。
| 一般墓 | 80万~300万円程度 |
|---|---|
| 公営や民間の墓地で新たに墓石を建てる場合、土地代と石材代が発生します。 | |
| 永代供養墓 | 5万~150万円程度 |
| 管理や供養を霊園や寺院に委託する合祀タイプの墓地です。 | |
| 納骨堂 | 10万~400万円程度 |
| 屋内に遺骨を安置する施設で、ロッカー式や個別納骨室など、形態の選択肢が豊富です。 | |
| 樹木葬 | 5万~200万円程度 |
| 樹木や花を墓標とする埋葬方法で、個別埋葬か合祀かで差が出ます。 | |
| 散骨 | 3万~70万円程度 |
| 遺骨を海や山に撒く埋葬方法です。立会いや代行などで費用が変動します。最近は宇宙散骨など新しい散骨も増えています。 | |
| 手元供養 | 数百円~60万円程度 |
| 遺骨を自宅で供養する方法で、遺骨を収める容器やアクセサリーの費用が中心です。 |
新しい供養方法を選ぶ際は、費用だけでなく故人や家族の意向も重視しましょう。散骨は再納骨ができないなど、後戻りできない方法もあるため慎重に検討が必要です。遠方の改葬先を選んだ場合、将来的な供養費用や訪問の手間も考慮する必要があります。
2-3. 行政手続きにかかる費用
墓じまいを進めるには、法律に基づいた行政手続きが必要です。手続きそのものは煩雑ではありませんが、書類取得に当たって以下の費用がかかる場合があります。
| 改葬許可申請書 | 無料~1,000円程度 |
|---|---|
| 改葬許可証を発行するための書類です。市区町村役場で取得します。 | |
| 埋葬証明書(納骨証明書) | 300~1,500円程度 |
| 現在の墓地管理者が発行する、遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。 | |
| 受入証明書(永代供養許可証) | 無料~1,500円程度 |
| 新たな納骨先で遺骨を受け入れることを証明する書類です。 | |
| 改葬許可証 | 無料~1,500円程度 |
| すべての書類をそろえた後、市区町村役場で発行されます。 |
改葬許可証は、遺骨1体ごとに発行が必要です。また、自治体によって必要書類は異なるため、事前に問い合わせることをおすすめします。
3. 墓じまいの費用は誰が負担する?払えない場合は?
墓じまいにかかる費用は、お墓の承継者が負担するのが一般的です。しかし、絶対的な決まりはないため、特に費用が高額な場合、複数名の親族で負担し合う場合もあります。
最近では終活の一環として、生前に自分で墓じまい費用を準備する人も増えてきました。まずは、遺言書や貯金などを確認するとよいでしょう。
費用を用意できない場合は、兄弟や親族に相談して協力を仰ぐのが第一歩です。お墓は家族や親族全体に関わるものであるため、一人で抱え込む必要はありません。また、一部の自治体では補助金制度を設けており、条件を満たせば支援を受けられます。
4. 墓じまいの費用を安く抑えるポイント

墓じまいにかかる費用は高額になりがちですが、工夫次第で節約が可能です。以下では、費用を抑える方法を2つ紹介します。
●複数の撤去業者から相見積もりをとる
墓石撤去にかかる費用は業者ごとに異なります。同じ作業でも数十万円以上の差が出る場合があるため、複数の業者から相見積もりを取るようにしましょう。費用を比較すれば、適正価格を把握しやすくなります。
ただし、撤去後の墓石が不法投棄されるリスクを避けるため、許認可を取得した信頼できる業者を選ぶことが重要です。また、墓地や霊園によっては工事業者が指定されている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
●納骨先をしっかり選ぶ
納骨先の選択は費用を大きく左右します。中でも、合祀墓や散骨などの選択肢は費用を抑えやすい方法です。合祀墓は他人の遺骨と一緒に埋葬するため、費用が比較的低く抑えられます。散骨は遺骨をパウダー状にし、自然に還す方法で、管理費などが不要です。ただし、いずれも実施後の取り返しはつかないため、慎重に検討しなければなりません。
また、納骨堂も費用を抑えつつ利便性が高いことで人気の選択肢です。駅近や天候に左右されない環境でのお参りが可能で、合祀タイプでなければ転居に合わせて移動させることもできます。
納骨先を選ぶ際は、費用面だけでなく家族や親族との話し合いも欠かせません。適切な納骨方法を選べば、墓じまいを円滑に進められるでしょう。
まとめ
墓じまい全体の費用は約30万~300万円と幅があり、一般的には承継者が負担しますが、親族で協力するケースや生前に準備する例も増えています。
墓じまいは、墓石の撤去や新たな納骨先の選定、行政手続きなどを含む複雑な作業です。遠方などで役所への対応が難しい場合には、専門業者に依頼する方法もあります。
費用を抑えるためには、納骨堂や合祀墓など費用を抑えられる納骨先を選ぶことが重要です。費用が支払えない場合には、自治体の補助金制度を活用する手段もあります。家族や親族との話し合いを重ね、自分たちに合った選択肢を探せば、墓じまいを円滑に進められるでしょう。