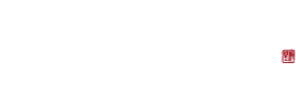葬儀費用の負担を軽減できる「葬祭費補助金制度」とは?申請方法も

この記事を書いた人
大切な人との別れは、突然訪れることもあります。心の整理もつかないまま深い悲しみに包まれる中で、それでも現実として向き合わなければならないのが、葬儀にかかる費用や手続きといった負担です。
葬儀に関する経済的な不安に直面したとき、残された家族の負担を少しでも和らげるためには、「公的な支援制度の活用」もひとつの手段となります。そして、葬儀に関する代表的な支援制度が「葬祭費補助金制度」です。
そこで今回は、葬祭費補助金制度の概要から、給付される補助金の種類、申請方法や注意点までを分かりやすく解説します。葬儀費用に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 葬儀費用の助けとなる「葬祭費補助金制度」とは?

葬祭費補助金制度とは、亡くなった方が加入していた公的保険制度などに応じて、葬儀を行った喪主(遺族)に一定額の給付金が支給される制度です。葬儀費用の全額を補助するものではないものの、突然の出費やそれによる経済負担に対する支援として活用できる制度となっています。
葬祭費補助金制度の対象となる公的保険制度は、国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険などのほか、生活保護も含まれます。故人が生前どの公的保険制度に加入していたかによって、給付金の名称や金額、申請先が異なります。
| 概要 | 亡くなった方が加入していた公的保険制度などに応じて、一定額の給付金が支給される制度 |
|---|---|
| 支給対象 | 葬儀を行った喪主(遺族) |
| 対象となる 公的保険制度 |
● 国民健康保険 ● 後期高齢者医療保険 ● 社会保険 ● 共済組合 ● 労災保険 ● 生活保護 |
2. 葬祭費補助金制度で給付される主な補助金の種類

葬祭費補助金制度では、故人が生前に加入していた保険制度に応じて、下記4種類の補助金のいずれかを受け取ることができます。
| 種類 | 対象となる公的保険制度 |
|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療保険 |
| 埋葬料・埋葬費 | 社会保険・共済組合 |
| 葬祭料 | 労災保険 |
| 葬祭扶助 | 生活保護 |
それぞれ給付条件や金額、申請先が異なるため、状況に応じた正しい制度を把握しておくことがまず大切です。ここからは、各補助金の詳細を解説します。
2-1. 葬祭費【国民健康保険・後期高齢者医療保険】
葬祭費は、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合に支給される補助金です。
葬祭費の具体的な支給金額は、地域によって異なります。自治体によっては葬祭費の給付を行っていない場合もあるため、なるべく早い段階で問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
また、申請は故人の住所地の役所で行い、申請者は原則として葬儀を執り行った喪主です。申請期限は「葬儀を行った日から2年以内」と定められています。
2-2. 埋葬料・埋葬費【社会保険・共済組合】
埋葬料・埋葬費は、故人が生前会社員や公務員などで健康保険や共済組合に加入していた場合に支給される補助金です。葬祭費とは異なり、葬儀そのものにかかった費用ではなく、埋葬するまでにかかる火葬費用や僧侶への謝礼、霊柩車代に対する補助金として支給されます。
扶養家族など遺族が埋葬を行った場合は、5万円を上限として埋葬費が支給されます。ただし、「家族以外が喪主となった」など支給要件を満たさない場合には、「埋葬費」として実際にかかった費用の実費分が支給されます。
このように、葬儀を行った喪主と故人が「生計をともにする関係にあったかどうか」によって、埋葬費か埋葬料かが変わることを覚えておきましょう。
申請先は故人が加入していた健康保険組合や勤務先を通じて行い、申請期限は原則として「故人の死亡日から2年以内」とされています。
2-3. 葬祭料【労災保険】
葬祭料は、故人が業務中や通勤中の災害によって亡くなった場合に労災保険から支給される補助金です。
葬祭料では、原則として下記2つのうち、いずれか高いほうが支給されます。
(2)給付基礎日額の60日分
葬祭料の請求は、葬儀を行った喪主が故人の勤務先を所轄する労働基準監督署で行います。申請期限は故人の死亡日から2年以内ですが、労災認定までに時間を要することがあるため、早めの相談・準備が大切です。
2-4. 葬祭扶助【生活保護】
葬祭扶助とは、生活保護法第18条に基づいて支給される扶助の一種で、故人または葬儀を行う遺族が経済的に困窮している場合に、自治体から支給される葬儀費用の補助金です。
支給の前提として、まず故人が生活保護を受けていた、または同等に経済的困窮状態にあり、葬儀費用をまかなえるだけの資産を残していないことが求められます。そのうえで、以下のいずれかに該当する場合に葬祭扶助の対象となります。
● 故人に扶養義務者がおらず、遺族以外の第三者(民生委員や家主など)が葬儀を手配する場合
たとえ故人が生活保護受給者だったとしても、遺族に一定の収入や資産がある場合は支給対象外となる点には特に注意しておきましょう。
また、支給額の基準は「直葬(火葬のみを行う簡易的な葬儀)」など最低限の内容を前提としています。そのため、一般的な葬儀を行う場合、補助でまかなえる範囲が限られてしまう点に注意が必要です。
葬祭扶助の申請は原則として「葬儀前」に福祉事務所に相談し、事前承認を得る必要があります。そのため、葬儀社に葬儀を依頼する前にまずは福祉事務所へ連絡し、支給の可否や内容について確認しておくことが大切です。
3. 葬祭費補助金制度の申請方法

葬祭費補助金を受け取るためには、いくつかの手続きが必要です。
ここでは、葬祭費補助金制度の申請を行う際の基本的な流れを、3つのステップに分けて詳しく解説します。
3-1. (1)資格喪失手続きを行う
葬祭費補助金を申請するには、まず故人が加入していた保険制度にて「資格喪失手続き」を行い、保険証を返却する必要があります。
国民健康保険の場合は自治体で手続きを行います。すでに葬儀が済んでいる場合は、葬祭費の申請も同時に行えます。保険種別や自治体によって具体的な必要書類や提出方法は異なるため、事前に確認しておくと安心です。
3-2. (2)必要書類を揃える
補助金の申請には、いくつかの必要書類を揃える必要があります。
一般的には、「申請書」「故人の保険証」「死亡を証明する書類(死亡診断書や火葬許可証)」「喪主であることを示す書類(会葬礼状や葬儀の領収書など)」「振込先口座情報」などが求められます。
加入保険の種類や自治体によってもやや異なり、書類の不備があると受理されない場合もあるため、申請前に窓口や公式サイトで確認することが大切です。
3-3. (3)該当窓口で申請手続きを行う
必要書類が揃ったら、該当する窓口にて申請を行います。国民健康保険や後期高齢者医療制度であれば市区町村の役所、社会保険であれば勤務先または協会けんぽ、労災保険であれば労働基準監督署、生活保護の葬祭扶助であれば福祉事務所が窓口です。
申請は原則として喪主が行い、期限は多くの制度で「葬儀を行った日、または死亡日から2年以内」となっています。期間を過ぎると申請できないため、早めの手続きを心がけましょう。
4. 葬祭費補助金制度の申請時におさえておくべきポイント

葬祭費補助金は、埋葬や葬儀にかかる費用の助けとなる制度です。しかし、正しく申請しなければ受け取ることができません。経済負担を少しでも軽減させるためにも、申請時のポイントをおさえておきましょう。
ここでは、申請時に特に注意しておきたい3つのポイントを紹介します。
4-1. 申請は基本的に「喪主」が行う
葬祭費補助金の申請者は、基本的に「喪主」であることが求められます。喪主とは、葬儀を主催し費用を負担した人を指し、故人の家族や親族となることが一般的です。
役所や保険機関に提出する書類では、喪主であることを証明するために、会葬礼状や葬儀の領収書などの提出を求められるケースもあります。家族内で誰が申請するかを事前に確認しておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。
4-2. 給付金申請期間(2年)を過ぎると失効する
葬祭費補助金には申請期限があり、多くの制度では「死亡日または葬儀を行った日から2年以内」と定められています。この期間を過ぎると時効となり、補助金を受け取ることができなくなるため注意が必要です。
特に、身内の死後は事務手続きが多く慌ただしいため、うっかり申請を忘れてしまうことも少なくありません。忘れないようにスケジュールに組み込む、または葬儀後なるべく早く申請するよう心がけましょう。
4-3. 給付金が振り込まれるまでには時間差がある
申請が受理されたあと、すぐに給付金が振り込まれるわけではありません。支給までの期間は制度や自治体によって異なりますが、一般的には1か月〜2か月程度かかることが多いです。
申請書類に不備があった場合や、自治体の審査に時間を要する場合は、さらに時間がかかることもあります。あらかじめこの時間差を考慮して、自己資金での一時的な対応を見越しておくと安心です。
まとめ
葬儀にかかる費用は、突然の不幸に見舞われた際には遺族の大きな負担となります。そうした際に助けとなるのが、各種公的制度によって支給される葬祭費補助金です。
葬祭費補助金制度を活用すれば、故人が加入していた保険の種類や生活状況に応じて、適切な補助金を申請できます。しかし、申請には期限や条件があるため、申請の流れや基本ポイントをしっかり押さえておくことが大切です。
葬儀の負担を少しでも軽減するためにも、制度を正しく理解し、適切に活用しましょう。