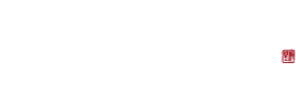葬儀費用の積立制度とは?利用メリット・主な分類も徹底解説!

この記事を書いた人
自身の人生に終わりが訪れるとき、または大切な家族の人生の終わりを迎えるとき、避けて通れないのが「葬儀費用」の問題です。突然の出来事によって、残された家族に大きな経済的・精神的負担を及ぼしてしまうケースも少なくありません。そのため、あらかじめ備えを整えておくことが大切です。
その中でも「葬儀費用の積立制度」は、必要な費用を計画的に準備できる仕組みとして注目されています。葬儀保険との違いや利用メリットを理解することで、自分や家族に適した備え方を選択できるでしょう。
そこで今回は、葬儀費用の積立制度の基本的な仕組みやメリット、代表的な制度の種類について分かりやすく解説します。
目次
1. 葬儀費用の積立制度とは?

葬儀費用の積立制度とは、将来の葬儀に備えて毎月一定額を積み立て、必要なときにその資金を葬儀費用に充てられる仕組みのことです。
突然の葬儀に直面した場合は多額の資金が必要となり、遺族に経済的・精神的に大きな負担を及ぼす可能性があります。事前に葬儀費用を積み立てられるこの制度は、家族全員にとっての安心材料の1つと言えるでしょう。
なお、葬儀費用の積立制度には大きく「互助会制度」と「民間事業者による独自制度」の2種類があります。いずれも実際にかかる葬儀費用をすべて賄えるわけではなく、あくまで「費用の一部をカバーするもの」である点に注意が必要です。
1-1. 葬儀費用の積立制度と葬儀保険の違い
葬儀費用の積立制度と混同されやすい制度に、少額短期保険の一種で掛け捨て型の「葬儀保険」があります。
積立制度は、毎月積み立てた金額をそのまま葬儀費用に充当する「前払い型」の仕組みであるのに対し、葬儀保険は掛金を支払い続けることで、万一の際にあらかじめ定められた保険金が給付される「保障型」です。
葬儀費用の積立制度と葬儀保険は、仕組みや利用条件にも違いがあります。
| 積立制度 | ● 年齢制限がなく誰でも利用できる ● 途中解約で返戻金が支払われるケースもある ● 手数料等の影響で元本割れする可能性もある |
|---|---|
| 葬儀保険 | ● 年齢制限が設けられていることが多い ● 解約返戻金はない場合がほとんど ● 元本割れする可能性もある |
どちらが優れているというよりも、経済的な余裕や「どの程度の範囲まで備えておきたいか」によって適切な選択は変わってきます。毎月コツコツと前払いで備えたい方には積立制度が向いており、少ない掛金で保障を得たい方には葬儀保険が適しています。
両者の仕組みを理解し、自分や家族の状況に応じて選び分けることが大切です。
2. 葬儀費用の積立制度を利用するメリット

突然の葬儀ではまとまった費用を一度に用意しなければならず、残された家族に大きな負担となることも少なくありません。あらかじめ積立制度を利用しておけば、経済的・精神的な負担を軽減できるうえ、実際の葬儀を滞りなく進める助けになります。
ここからは、葬儀費用の積立制度を利用するメリットをより詳しく説明します。
2-1. 万一の際の経済的負担を軽減できる
葬儀には、100万〜200万円程度の費用がかかると言われています。大切な家族の旅立ちを迎えて悲しみに打ちひしがれる中で、誰もがまとまった金額をスムーズに準備できるわけではありません。しかし、積立制度を利用すれば少額からコツコツと準備を進めることができ、万一の際の急な出費にしっかりと備えられます。
また、制度によっては解約返戻金が支払われる場合もあり、万一利用しなかったときにも一部が戻るケースもあります。こうした仕組みは、残される家族の金銭的な不安を和らげる大きなメリットと言えるでしょう。
2-2. 葬儀をスムーズに行える
突然の葬儀では、喪主や家族が短期間で葬儀社選びや費用の算出を迫られることが多く、大きな精神的負担にもなります。積立制度を利用しておけば、事前に葬儀の内容や費用がある程度決まっているため、万一の際にも落ち着いて準備を進められます。
また、会員向けプランが用意されているケースも多く、基本的な流れがあらかじめ整っているため当日もスムーズに進行しやすい点が特徴です。
2-3. 会員特典や割引サービスが受けられる
葬儀費用の積立制度では、積立利用者を会員として位置づけ、さまざまな特典を提供している場合があります。例えば、「葬儀プランの割引」「式場や控室の優先利用」「提携施設での割引サービス」などです。
なかには葬儀以外にも結婚式や法要、日常生活に役立つサービスに適用されることもあります。積立そのものが将来の備えになるだけでなく、加入中から日常的にメリットを享受できるのも魅力の1つと言えるでしょう。
3. 葬儀費用の積立制度の主な分類2つ

前述の通り、葬儀費用の積立制度と一口に言ってもその仕組みは一様ではなく、大きく分けて「冠婚葬祭業者が運営する互助会制度」と「葬儀社や生活協同組合(コープ)などの民間事業者が提供する独自の積立制度」の2種類があります。
いずれも将来の葬儀に必要な費用を前払い形式で計画的に準備できる点は共通していますが、運営主体や契約内容、受けられるサービスの範囲などに違いがあります。
特に民間事業者による制度では「コープの家族葬つみたて制度」などが代表的で、互助会とは異なる特徴をもちます。ここからは、各制度の仕組みやメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。
3-1. 互助会による葬儀費用の積立制度
互助会による葬儀費用の積立制度とは、冠婚葬祭業者が提供する会員制サービスの1つで、毎月一定額を積み立てることで将来の葬儀や結婚式などに利用できる仕組みです。
法律上は「割賦販売法」に基づいて運営されており、会員が支払った掛金は経済産業省に届け出た範囲で保全される仕組みとなっています。
【互助会による葬儀費用の積立制度のメリット】
● 葬儀の基本プランがあらかじめ用意されており、手続きが比較的スムーズ
● 葬儀のほか結婚式や法要などにも利用できる
● 会員割引や特典サービスが受けられる
【互助会による葬儀費用の積立制度のデメリット】
● 利用できる葬儀社・式場が限定される
● プラン内容が固定的で、柔軟性に欠ける場合がある
● 葬儀費用のすべてをまかなえず、追加費用が発生するケースも多い
互助会は長年の実績があるため信頼性が高く、全国的にも加入者が多い点が特徴です。「必要最低限の枠組みを用意する制度」という色合いが強く、追加オプションやサービスを選ぶと総額は高くなる傾向がある点に注意しておきましょう。
3-2. 民間事業者による独自の葬儀費用積立制度
民間事業者による独自の積立制度は、葬儀社や生活協同組合などが独自に提供している仕組みで、代表的なものに「コープの家族葬つみたて制度」が挙げられます。生活協同組合が運営するため信頼性が高く、家族葬ニーズの増加によって近年さらに人気を集めています。
【民間事業者による独自の葬儀費用積立制度のメリット】
● 利用範囲やサービス内容が比較的柔軟で、ニーズに合わせやすい
● 一括払い・分割払いなど、支払い方法を選べる場合がある
● 会員特典や割引サービスが付帯することが多い
【民間事業者による独自の葬儀費用積立制度のデメリット】
● 互助会に比べると加入者数が少なく、地域によっては選択肢が限られる
● あくまで費用の一部をカバーする制度であり、追加費用が発生することもある
● 制度によっては、途中解約に条件が付く場合がある
互助会による葬儀費用の積立制度と比べて自由度は高いものの、事業者ごとの規約や運営方針に違いがあるため、契約前に必ず確認しておくことが大切です。
4. 葬儀費用の積立制度はあくまで選択肢の1つとして考えることが大切

葬儀の小規模化や多様化が進む近年、葬儀費用の積立制度がすべての方に適しているとは限りません。まずは「どのような葬儀や納骨を望むのか」を明確にし、葬儀社などと相談しながら必要な費用感を確認することが大切です。
自分や家族が望む葬儀が貯金・預金から支払える程度の低価格なものであれば、元本割れや利用制限といったリスクを伴う積立制度をあえて利用する必要はありません。
葬儀費用の積立制度はあくまで「万一に備えるための選択肢」の1つとして、自分や家族の希望や経済状況と照らし合わせながら検討することが大切です。
まとめ
葬儀費用の積立制度は、万一の際にかかる葬儀費用を計画的に準備できる仕組みとして多くの方に注目されています。大きく互助会による積立制度と民間事業者による積立制度があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。
近年は葬儀の小規模化や多様化が進んでおり、日頃の貯金や預金で満足できる葬儀を行えるケースもあります。そのため、積立制度を利用するかどうかは経済状況や家族の希望に応じて判断することが大切です。
了聞では、葬儀の事前予約をお勧めしております。
提携葬儀社の了聞契約者様特典や葬儀セットプランのご用意もございますので、お気軽にご相談ください。