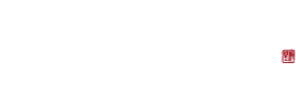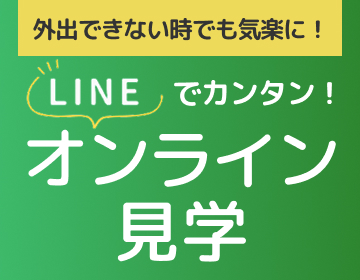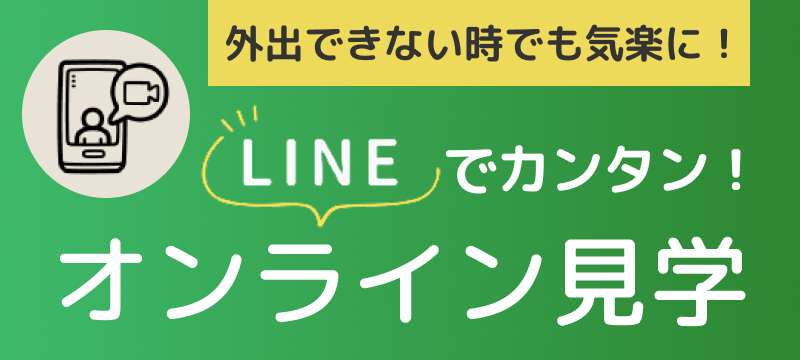回忌とは?年忌法要の数え方・弔い上げのタイミング・よくある質問も

この記事を書いた人
故人の年忌法要が営まれるとき、その法要を指して「○回忌」と呼びます。年忌法要を執り行う施主の方や、法要に招かれた参列者の方は「回忌とはどのような意味があるのだろう」と疑問を持つことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、回忌の概要から年忌法要の数え方と弔い上げのタイミング、さらに年忌法要の準備の流れまで詳しく解説します。回忌に関するよくある質問と答えも紹介しているため、年忌法要に関わる方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 回忌とは?

回忌とは、故人が亡くなったときと同じ月・同じ日を指す「祥月命日」に執り行う年忌法要のことです。
回忌は、三回忌や七回忌のように「数字+回忌」という表記で使われます。回忌の前に来る数字は故人が迎えた命日の回数を示していて、「今年で故人が亡くなって○年なんだな」と時の流れを意識できるでしょう。
そもそも法要は、大きく分けて忌日法要と年忌法要の2種類があります。
| 忌日法要 | 故人が亡くなった日(忌日)から特定の日数で執り行われる法要 |
|---|---|
| 年忌法要(回忌法要) | 故人が亡くなった翌年以降、特定の年数で執り行われる法要 |
回忌は年忌法要で使われる表現であり、忌日法要のうちは回忌と呼ばれることはありません。
年忌法要では、特定の年数における祥月命日に遺族・親族が自宅や寺院に集り、法要を執り行います。お坊さんによる読経と遺族・親族の焼香で故人を供養して、法要後は参列者で会食をして故人をしのぶという流れです。
2. 【早見表】回忌(年忌法要)の種類と数え方

回忌を数える際のポイントは、回忌の数字は最初の祥月命日を1回目としているということです。つまり〇回忌の年忌法要は「〇回目の祥月命日」を示しています。
注意したい点は、年忌法要は毎年ではなく数年おきに執り行う儀式であることです。執り行う年忌法要の種類と、回忌の数字との関係性が分からなくなったときは、下記の早見表を参考にするとよいでしょう。
| 一周忌 | 命日から満1年 | 亡くなってから2回目の祥月命日 |
|---|---|---|
| 三回忌 | 命日から満2年 | 亡くなってから3回目の祥月命日 |
| 七回忌 | 命日から満6年 | 亡くなってから7回目の祥月命日 |
| 十三回忌 | 命日から満12年 | 亡くなってから13回目の祥月命日 |
| 十七回忌 | 命日から満16年 | 亡くなってから17回目の祥月命日 |
| 二十三回忌 | 命日から満22年 | 亡くなってから23回目の祥月命日 |
| 二十五回忌 | 命日から満24年 | 亡くなってから25回目の祥月命日 |
| 二十七回忌 | 命日から満26年 | 亡くなってから27回目の祥月命日 |
| 三十三回忌 | 命日から満32年 | 亡くなってから33回目の祥月命日 |
| 五十回忌 | 命日から満49年 | 亡くなってから50回目の祥月命日 |
回忌を執り行う時期に迷ったら、「回忌-1」の式で計算するとすぐに分かります。
たとえば2019年に亡くなった方の七回忌を執り行うタイミングは、「七回忌-1=命日から満6年」となり、「2019年+6年」と計算して2025年です。
2-1. 「一回忌」と「一周忌」の違い
一回忌と一周忌はいずれも「一(1)」が付くためしばしば混同されるものの、それぞれが指す日には明確な違いがあります。
一回忌とは、故人にとって1回目の命日で、つまり亡くなった当日を表す言葉です。故人の葬儀が一回忌に行われる法要となりますが、葬儀を指して一回忌と呼ぶことはほとんどありません。
対して一周忌とは、故人の1回目の命日から満一年が経った日、つまり一回忌に対して翌年の祥月命日のことです。一周忌に行われる法要は「一周忌法要」と呼びます。
なお、故人の命日から一周忌までの期間は喪中であり、一周忌には喪明けの意味合いがあります。そのため一周忌は年忌法要の中でも特に重要とされていて、一周忌法要は葬儀と同じくらいの規模で盛大に執り行われることが多い傾向です。
3. 年忌法要はいつまで行う?

年忌法要(回忌法要)の中でも、最後に執り行う年忌法要は「弔い上げ」、または「問い上げ」「揚げ斎(あげとき)」と呼ばれます。
弔い上げは「故人の魂は安らかに眠った・旅立った」と見なす意味合いがあり、弔い上げを行った後には年忌法要を開くことはありません。
弔い上げの時期は明確に定められてはおらず、地域や家庭の慣習、さらに信仰する宗派によってそれぞれ異なります。一般的には「三十三回忌」を最後として、弔い上げという形で年忌法要を終了することが多い傾向です。
三十三回忌が弔い上げの時期として選ばれる理由は、仏教では故人の魂は33年目に最後の審判を受けると考えられていて、節目の年に当たるためです。
また、死後30年以上も経つと遺族・親族が世代交代をして、故人を知っている人が少なくなる点も、三十三回忌が弔い上げの時期とされている理由でしょう。
三十三回忌の他にも、弔い上げとして選ばれることが多い年忌法要には「十七回忌」と「五十回忌」が挙げられます。
十七回忌は多くの仏教の宗派で節目の法要と考えられていて、弔い上げを早めたいときに適したタイミングです。
一方で五十回忌は、日本の伝統的な仏教の場合、死後50年(五十回忌) を迎えると、個人の供養の区切りとして弔い上げを行い、「故人の魂が安らかに旅立った」とみなす風習があります。三十三回忌よりも多く供養をしたいときの弔い上げに適しています。
しかし近年では核家族化などの事情によって、七回忌以降は規模を縮小したり、いくつかの法要を省略したりする傾向も強まっています。
4. 年忌法要の主な準備の流れ
年忌法要を執り行う施主や遺族の方は、年忌法要を以下の流れで準備しましょう。
| (1) | 法要の日程・会場を決める |
|---|---|
| (2) | 案内状を作成・送付する |
| (3) | 会食で出す食事を手配する |
| (4) | 参列者の人数分の返礼品を用意する |
ただし、法要の規模を縮小する場合はより簡単な流れとなります。たとえば遺族だけで年忌法要を営み、会食や返礼品も用意しないケースでは、(1)の法要の日程・会場を決めるだけで法要の準備は完了します。
また、読経を上げてくれるお坊さんに渡す「お布施」の準備も必要です。お布施で用意するべき額は地域の慣習や宗派、法要の規模によって異なるものの、おおむね1万~5万円が相場とされています。
5. 回忌(年忌法要)に関するよくある質問【Q&A】

回忌は頻繁に行われる法要ではないため、今まで執り行った経験があまりない方や、年忌法要そのものにあまり参列したことがない方は多いでしょう。
回忌に関して「このようなケースではどうすればいい?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
最後に、回忌(年忌法要)に関するよくある3つの質問と答えを解説します。
5-1. Q1:祥月命日に法要を行えない場合はどうすれば良い?
祥月命日に法要を行えない場合は、法要の日取りを遺族や親族の都合がよい日に調整します。法要に参列する遺族・親族と話し合って、参列者全員が集まれる日を選ぶとよいでしょう。
ただし、日本では「仏事は先延ばしにしない」という慣習があります。法事の日取りを調整するときは、祥月命日よりも前倒しの日程にすることが一般的です。
5-2. Q2:親戚は何回忌まで呼ぶ?
親戚を何回忌まで呼ぶべきかは明確な基準がないため、遺族・親族間で話し合って決めるとよいでしょう。
一般的には、三回忌までは親族を年忌法要に招くことが多い傾向です。三回忌は故人の命日から満2年とそれほど年数があいていないため、親戚を招かないと「そろそろ三回忌なのに案内状が来ない」と感情を害する可能性があります。
七回忌以降に法要の規模を縮小する場合は、規模の縮小に合わせて参列者を減らすことを検討するとよいでしょう。
5-3. Q3:年忌法要のときの服装は?
年忌法要のときの服装は、三回忌までは遺族も参列者も「喪服(準喪服)」を着ることが基本です。ブラックスーツ・ブラックフォーマルを着て、過度な露出や派手すぎるアクセサリーの着用を控えれば問題ありません。
七回忌以降は平服でよいとされています。
ただし、法事における平服とは「略喪服」のことです。平服=普段着ではないため、カジュアルな服装で参列しないように注意してください。
まとめ
回忌とは、故人が亡くなってから特定の年数ごとの祥月命日に執り行う年忌法要のことです。
故人が亡くなった翌年の祥月命日に執り行う年忌法要を「一周忌」と呼びます。以降は三回忌・七回忌といった順番で行い、「回忌-1」で計算すると命日から何年経過したかが分かります。
弔い上げのタイミングや年忌法要の準備については、紹介した内容を参考に考えるとよいでしょう。回忌を詳しく知ることで、年忌法要に参列するときはもちろん、自分が施主となったときにもスムーズに準備を進められます。