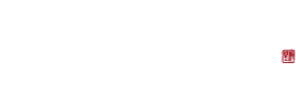親が亡くなる前にやること12選|悔いのない形で最期を見送るために

この記事を書いた人
親と過ごせる時間には限りがあり、いつかは別れのときがやってきます。自分の親と過ごせる残りの時間が短いことが分かっている方は、悔いのない形で最期を見送れるように準備をしておきましょう。
手間のかかる手続きや体力が求められる作業をサポートすることで、親は残された時間を不安なく過ごせます。
今回は、親が亡くなる前にやっておくべきことを詳しく解説します。
目次
1. 親が亡くなる前にやっておくべきこと12選

親が亡くなる前にやっておくべきことは、各種手続きや身の回りの整理などさまざまです。希望に沿った形で最期を迎えられるように、生前から準備しておくことが大切です。
また、事前準備をしているかどうかによって、亡くなった直後の各種手続きの大変さも大きく変わります。
以下では、親が亡くなる前にやっておくべきことを理由とともに詳しく解説します。
1-1. 銀行口座からまとまったお金を引き出す
親が亡くなると、病院への治療費の支払いや葬儀費用の支払いが発生するため、銀行口座からまとまったお金を引き出しておくと安心です。
銀行は名義人の死亡を確認後、預金口座を凍結します。口座凍結されると、お金を引き出すために書類の用意が必要となり手続きに時間がかかります。
また、貸金庫や定期預金にお金がある場合も同様です。使用頻度の低い口座や貸金庫は、解約したり残高をまとめたりしておきましょう。
銀行が名義人の死亡を確認する前であれば、預金口座から現金を引き出すことは可能です。しかし、他の相続人から財産の独占を疑われてトラブルになることがあるため、注意しましょう。
1-2. 加入保険の契約内容を確認する
親が生命保険に加入している場合、亡くなった後に指定受取人に保険金が支払われます。生命保険の保険金は遺産分割の対象になりません。
離婚や家族構成の変化があったタイミングで契約内容の見直しをしていない場合、前の配偶者や故人が受取人になっている可能性もあります。希望しない形で保険金が支払われることもあるため、受取人が誰になっているのか生前に確認しておきましょう。
受取人を変更するためには、契約者本人による手続きが必要です。
1-3. 生前整理を行う
自宅の不用品を整理することで、身の回りをすっきりさせて快適に生活できるようになります。生前整理には手間と時間がかかるため、少しずつ取り組むことがポイントです。
生前整理を行うことは、相続財産の把握にもつながります。通帳や土地の権利書など、大事な書類をまとめておくことで、親が亡くなった後の手続きがスムーズになるでしょう。
「使うもの」「不要なもの」「形見分けするもの」の3つに分類すると、生前整理を進めやすくなります。ただし、トラブルの原因にならないように、本人の意思を尊重しましょう。
1-4. 財産目録を作成する
親が保有する財産を把握するために、財産目録を作成しましょう。財産目録に記載する主な項目は、下記の通りです。
| プラスの財産 | ● 土地 ● 家屋 ● 預貯金 ● 上場株式 ● 非上場株式 ● 出資金 ● 投資信託 |
|---|---|
| マイナスの財産 | ● 借入金 ● ローン |
親の財産を把握できていれば、亡くなった後の遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが上回る場合は、相続放棄も選択肢の1つです。
財産目録を作るにあたっては、親から話を聞くだけでなく各事業者に問い合わせて確認することが大切です。
1-5. 各種資産・契約の名義を変更する
各種資産や契約の名義変更をすることで、相続税対策になる可能性があります。親の死亡日から3年前に不動産や銀行口座などの名義が子に変更されていた場合、生前贈与とみなされ贈与税の対象になります。課税免除になる資産であれば、税金対策に効果的です。
また、生前贈与により相続財産が少なくなれば、親が亡くなった後に発生する相続税を減らせます。ただし、親の死亡日から3年以内に名義変更した資産や契約に関しては、相続税の対象となることを理解しておきましょう。
1-6. デジタル情報を管理する
スマホやパソコン内のデジタル情報は、アクセスや退会などの操作にパスワードやIDが必要となります。親が亡くなった後でデジタル情報を管理したくても、パスワードやIDが分からなければスムーズに対処できません。
不要なデータの処分や必要なデータの保存、使っていないサブスクリプションの解約など、必要に応じて管理をサポートすることも大切です。FXや仮想通貨、電子マネーなどのデジタル資産もしっかり把握しておきましょう。
1-7. 遺言書を作成してもらう
遺言書は、自身が保有している財産を死後にどのように相続させたいかを示す書面です。遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書を作成してもらうことで、親が希望する形で財産を分けられます。
遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかを用いるのが一般的です。自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成して亡くなったことを知った日から遅滞なく家庭裁判所の検認を受けます。検認を受けずに済む「自筆証書遺言保管制度」を活用する方法もあります。この場合、事前に法務局に保管申請の手続きをしておく必要があります。公正証書遺言は、2人の証人の立会いのもとに公証人が作成します。
正式な遺言書を作成するには条件を満たす必要があるため、専門家に相談しながら作成しましょう。
1-8. 戸籍謄本を取り寄せる
法定相続人を把握する場合、戸籍謄本を取り寄せて内容を確認するのが確実です。戸籍謄本には、親族関係や個人の身分事項などが記載されています。
戸籍謄本は、不動産や銀行口座の名義変更にも必要です。戸籍謄本の枚数は人によって異なり、結婚や離婚を繰り返していた方や転勤や引っ越しで本籍地を何度も移転していた方は、枚数が多くなります。
戸籍謄本の取り寄せは、本籍地の市区町村役場で交付請求するか郵送請求ができます。生前であればマイナンバーカードを利用してコンビニ交付も可能ですが、亡くなった後はコンビニ交付ができないため注意しましょう。
1-9. 相続税の試算をする
相続税は、故人の財産が基礎控除を超える場合に相続人が支払わなければならない税金です。故人の財産によっては相続税が発生するため、あらかじめ試算をしておきましょう。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。父親が亡くなり、母と子ども3人が法定相続人となる場合、「3,000万円+600万円×4」で5,400万円が控除されます。
納めるべき相続税額は、控除後の金額に応じて10~55%の税率で計算する決まりです。
1-10. 遺影を撮影する
親が亡くなってから慌てて遺影に使う写真を探す家庭も多く見られます。「この写真を使ってほしい」「この写真は嫌だ」など本人の希望がある場合も多いため、一度遺影について話し合っておくことが大切です。
遺影用の写真を新たに撮る場合は、納得のいく遺影にするためにも体力があるうちに撮影を済ませておきましょう。画像の加工を行う専門業者もあるため、お気に入りの写真がある場合は加工を依頼するのもおすすめです。
1-11. 葬儀社・葬儀プランを選ぶ
亡くなった直後は手続きに追われるため、ゆっくりと葬儀について考える時間を取れません。本人の要望をできるだけ反映できるように、話し合いの時間を持つことも大切です。
葬儀方法が多様化していることもあり、自分の葬儀に要望がある方が増えています。家族だけで見送ってほしい方もいれば、盛大に見送ってほしい方もいます。葬儀のスタイル・規模・参列者の人数などを確認して、要望に合う葬儀社・葬儀プランを選びましょう。
1-12. 生前墓の購入・寿陵をする
葬儀を行った後に遺骨をどうするかも話し合っておく必要があります。お墓を新たに建てる場合は、相続税対策のために生前墓の購入・寿陵をするのがおすすめです。
親が生きているうちに購入したお墓や納骨堂、仏壇などは祭祀財産とみなされ非課税扱いとなります。しかし、お墓を購入するためにお金を残しておいた場合は、相続税の課税対象となるため注意しましょう。
お墓の価格相場は150万~250万円と言われています。まとまった費用がかかるため、生前に準備しておくことは相続税対策に効果的です。
まとめ
親が亡くなると、葬儀の手配や遺産相続の手続きなどに追われて慌ただしくなります。悔いのない形で最期を見送るには、親の時間と体力があるうちにできることから準備をしておきましょう。
葬儀費用を確保するために銀行口座からまとまったお金を引き出したり、財産目録や遺言書を作成したり、親が亡くなる前にやっておくべきことは多岐にわたります。
亡くなった直後の各種手続きもスムーズになるため、親の不安や家族の負担も軽減できるでしょう。